耳鼻科開業時に必要なホームページとは?タイミング・掲載内容・制作費用を徹底解説
2025-05-20
監修:久保谷 太志
経済産業大臣認定 中小企業診断士 / Web制作ディレクター
目次

耳鼻科の開業にホームページは必要か
結論から言えば、耳鼻科を開業する際にホームページは「必須」と言える存在です。
これは単なる宣伝目的ではなく、患者さんの信頼獲得・選ばれる理由の可視化・診療導線の整備といった観点から、重要な役割を果たすからです。
開業時のホームページが持つ 3 つの役割
① 地域の患者に「ここに耳鼻科ができる」と伝える告知ツール
多くの方は新しく病院を探す際、「耳鼻科 〇〇市」などのワードで Google 検索をします。
このとき公式サイトが存在していなければ、競合に流れてしまう確率が非常に高くなります。
とくに開業直後は、チラシや看板だけでは情報が十分に届かないため、Google 検索やマップ上での発見性=集患の第一歩になります。
② 患者にとっての「不安解消」と「安心材料」
初診の患者さんにとって、病院選びは不安の連続です。
- どんな先生なのか?
- 混雑していないか?
- 院内は清潔か?
- 予約はできるのか?
こうした疑問に答える「オンライン上の窓口」として、ホームページは非常に重要な役割を持っています。
③ スタッフ採用・求人の信頼性を高めるツールとしても有効
意外に見落とされがちですが、ホームページは求職者にとっても医院の人柄や雰囲気を知る手段になります。
採用情報ページや院内写真、スタッフメッセージなどを載せておくことで、共感や安心感を持って応募してもらいやすくなります。
耳鼻科開業時のホームページは“見込み患者との最初の接点”
開業してからではなく、開業準備の段階からホームページを用意することで、内覧会・予約受付・Google マップ登録などすべての動きがスムーズになります。
「診療だけでなく、伝え方でも信頼を得る」。
そんな医院を目指す方には、ホームページは欠かせないツールだといえるでしょう。
開業前からホームページがあると得られる 3 つのメリット
耳鼻科クリニックを開業する際、「開業してからホームページを作ればいい」と考える方も少なくありません。
しかし実際には、開業前からホームページを持つことで得られるメリットは非常に大きく、集患や運営準備をスムーズに進めるうえでも効果的です。
ここでは、開業前にホームページを準備することで得られる代表的な 3 つのメリットをご紹介します。
① 内覧会や開業日の告知ができ、事前に認知を獲得できる
開業予定日が決まっていても、地域の方にその情報が伝わっていなければ意味がありません。
ホームページがあれば、「○ 月 ○ 日新規開院」「内覧会開催のお知らせ」などを事前に周知するツールとして活用できます。
また、チラシや看板、SNS などから公式サイトへ誘導することで、より深い情報(診療方針・院内の雰囲気・アクセス方法など)を伝えることができ、信頼感につながります。
② スタッフ採用の応募率が上がる
開業前は人材採用も大きな課題のひとつです。
求人情報を出しても「どんな院なのか分からない」と不安を抱かれることもあります。
ホームページで「院長あいさつ」「院内設備の紹介」「スタッフ募集ページ」などを掲載しておくことで、応募者に安心感を与え、マッチ度の高い人材を確保しやすくなります。
③ Google マップや検索結果に事前に表示され、検索経由で認知される
多くの人が「耳鼻科 地域名」「花粉症 ○○ 駅」などで検索する中、Google 検索・マップ上に情報が出ることは集患の第一歩になります。
ホームページを先に公開しておけば、Google ビジネスプロフィールの登録も早めに可能になり、マップ検索での表示も先手を打てます。
これにより、開業初日から予約や来院につながるケースも実際に増えています。
開業前こそ「認知」「信頼」「準備」が整うチャンス
ホームページは開業後のためだけではありません。
むしろ、開業前だからこそできる情報発信・集患・採用の下準備があります。
早めに公開しておくことで、スタートダッシュの質が変わります。
開院日を迎える頃には、すでに地域に認知されている状態を目指しましょう。
耳鼻科ホームページの公開タイミングはいつがベストか
ホームページの重要性が分かっても、「いつ作ればいいの?」「開院日までに間に合うのか不安…」という声は少なくありません。
結論から言えば、ホームページは“開業の 1〜2 ヶ月前までに公開”するのが理想的です。
ここでは、なぜその時期がベストなのか、公開タイミングによって得られる効果を詳しく解説します。
開院の 1〜2 ヶ月前が最適な理由
① Google 検索に反映されるまでには時間がかかる
新しく公開したホームページが Google 検索に表示されるまでには、通常 1〜2 週間以上の時間がかかります。
さらに「耳鼻科 〇〇市」のような地域キーワードで上位表示を狙うには、最低でも 1 ヶ月程度の準備期間を見込んでおくのが安全です。
② 内覧会・プレオープンの情報発信ができる
開業前に内覧会や無料相談会を開催する医院も増えています。
その案内をホームページで発信できれば、地域の住民に安心感や親しみを与えられ、初診への心理的ハードルを下げる効果があります。
③ 採用情報や設備紹介など“準備段階”の情報も公開できる
院長プロフィール、導入設備、診療方針など、開院前でも公開できる情報はたくさんあります。
事前に「どんな医院なのか」を可視化しておくことで、求職者や患者からの信頼度を高めることができます。
開院直前や開業後では遅い理由
- 公開してすぐは検索に表示されにくい
- 「準備不足」の印象を与えてしまう
- 開業後は診療や対応で忙しく、制作に集中しづらい
こうした理由から、“ホームページは開院準備の一部”として、早めに着手することが非常に重要です。
ホームページは「開院の告知ツール」として先に出す
ホームページは“院の顔”であると同時に、開業のスタートを告げる告知媒体でもあります。
開業準備のスケジュールに合わせて、「1〜2 ヶ月前に公開」を目標にスケジュールを組みましょう。
早めに準備することで、集患・採用・地域認知すべてにおいて有利なスタートを切ることができます。
必ず掲載すべき耳鼻科ホームページの基本コンテンツ
耳鼻科クリニックのホームページを作るうえで重要なのは、「見た目」だけではありません。
患者さんが安心して来院できるようにするためには、必要な情報を過不足なく掲載することが不可欠です。
この章では、開業前・開業直後の耳鼻科にとって必ず掲載すべき基本コンテンツをわかりやすく整理します。
① 診療時間・休診日・アクセス情報(最優先)
最も基本かつ重要な情報です。
- 曜日ごとの診療時間
- 午前/午後の時間帯
- 休診日(祝日は診療?振替?)
- 地図(Google Map)と最寄り駅・バス停・駐車場情報
これらが明確であることで、患者さんが迷わずに来院するための大きな手助けになります。
② 対応している診療内容・症状一覧
耳鼻科は「花粉症」「中耳炎」「めまい」「アレルギー」など、症状によって患者層が異なる診療科目です。
以下のように、対応可能な内容をカテゴリごとに記載しましょう。
例:
- アレルギー性鼻炎・花粉症
- 中耳炎・外耳炎・難聴
- 喉の痛み・扁桃腺の腫れ
- 小児耳鼻科・キッズ対応
- めまい・耳鳴り・補聴器相談
これにより、自分の症状で受診してよいか判断しやすくなります。
③ 院長あいさつ・プロフィール
「どんな先生が診てくれるのか」は、患者にとって非常に大きな安心材料です。
院長の専門分野・これまでの経歴・診療に対する想いなどを写真付きで丁寧に紹介しましょう。
ポイント:
- 笑顔の写真(白衣姿がベター)
- 大学・病院などの経歴
- モットーや診療方針の一言
④ 院内設備・感染対策への取り組み
院内の様子がわかる写真(待合室・診察室・トイレなど)を掲載することで、初めての患者さんでも安心して来院しやすくなります。
特にコロナ以降は「感染対策の取り組み(換気・消毒・非接触決済など)」の明記があると好印象です。
⑤ よくある質問(FAQ)
「初診でも予約できますか?」「駐車場はありますか?」など、患者さんからよく聞かれる質問をまとめておくと便利です。
電話対応の手間も減らせるので、医院側にもメリットがあります。
⑥ お知らせ・ブログ
- 臨時休診のお知らせ
- スタッフ募集の告知
- 花粉症情報などの季節コンテンツ
これらを更新できるページがあると、最新情報を発信しやすく、サイトが「生きている」印象になります。
⑦ 予約・お問い合わせ導線
外部予約システムと連携する場合も、分かりやすいボタンやバナーで誘導を。
また、お問い合わせフォームや電話番号も、スマホでタップしやすい設計にしておきましょう。
基本情報は「患者さんの不安をなくす」ためにある
耳鼻科のホームページにおいては、「何を伝えるか」ではなく「患者さんが何を知りたいか」という視点で構成することが大切です。
ひとつひとつの情報が、信頼につながり、選ばれる理由になります。
患者に選ばれる耳鼻科サイトのデザインと構成のコツ
耳鼻科のホームページにおいて、**「見やすい」「使いやすい」「安心感がある」**という印象を与えるデザインは非常に重要です。
特に初診の患者さんや小さなお子さんを連れた保護者、高齢の方など、幅広い層にとってわかりやすいことが求められます。
ここでは、“選ばれる耳鼻科”になるために意識すべきデザインと構成のポイントを紹介します。
① 清潔感・安心感のあるカラーとフォントを選ぶ
医療系のサイトでは、白・ブルー・グリーン系の清潔感ある配色が基本です。
明るく落ち着いた色合いにすることで、信頼感・誠実さを演出できます。
- ✅ NG:黒・赤・蛍光色など、刺激の強い色
- ✅ OK:#f0f9ff(薄い水色)#eaf6f6(薄いグリーン)#ffffff(白) など
また、文字のフォントも丸ゴシックや読みやすい明朝体などを選び、“読みやすさ”を優先しましょう。
② スマホファーストで設計する(モバイル最適化)
現在、患者の6〜7 割以上がスマートフォンからサイトを閲覧していると言われています。
そのため、「スマホで見やすい設計」はもはや必須です。
- ボタンはタップしやすい大きさに
- 電話番号はワンタップで発信可能に
- メニューはハンバーガー式+固定ナビがベスト
- 予約・アクセスボタンは常に見える位置に設置
③ 写真やイラストで「雰囲気」を伝える
文章だけでなく、写真やイラストを活用して“空気感”を伝えることも重要です。
例えば:
- 院長の笑顔の写真
- 待合室・診察室の内観写真
- お子さま向けのやさしいイラスト
患者さんが「ここなら行ってみたい」と思える安心感を作りましょう。
④ 情報はシンプルに、導線は明確に
医療サイトにおいては「見た目の派手さ」よりも「迷わず情報にたどり着ける設計」が重要です。
✅ ページ内で特に重要なのは以下の 4 点:
- 診療時間・休診日
- アクセス(Google マップ)
- 対応している症状
- 予約・問い合わせ方法
これらはトップページからすぐに確認できるようにし、訪問者のストレスを減らしましょう。
⑤ CTA(予約・お問い合わせ)ボタンの配置にこだわる
「いいサイトだけど、どこから予約すればいいのかわからない…」
これは集患の大きな機会損失につながります。
- 画面右下に「24 時間 WEB 予約」ボタンを常時表示
- ファーストビューや記事末にも予約ボタンを設置
- ボタンの色は他と差別化して目立たせる(例:明るい青・緑)
患者が「この医院に行こう」と思った瞬間に、すぐにアクションできる導線を設けることが重要です。
選ばれるサイトは「使いやすく、やさしいデザイン」
患者さんが不安を抱えながらサイトに訪れるという前提に立つと、
親しみ・信頼・迷わなさをデザインの軸にすることが、耳鼻科ホームページにおける成功の鍵となります。
おしゃれさよりも、“伝わる・使いやすい”を優先することで、結果的に選ばれるサイトに近づきます。
ホームページから予約や問い合わせにつなげる仕組みとは
どれだけ見た目の良いホームページを作っても、「予約されない」「問い合わせが来ない」サイトでは意味がありません。
患者さんに「ここに行ってみたい」と思ってもらえた瞬間に、すぐ行動(=予約)に移してもらう仕組みを作ることが重要です。
ここでは、耳鼻科クリニックのホームページにおいて、予約・問い合わせを自然に促すための導線設計とツール活用のポイントを解説します。
① 予約ボタンは「目立つ位置」に常設する
- ファーストビュー(最上部)に目立つ色で「WEB 予約はこちら」ボタンを配置
- スマホ画面では右下固定のフローティングボタンが効果的
- ヘッダーやフッターにも必ず設置し、「どこからでも予約できる」安心感を与える
ボタンの色はサイト全体の中でも目立つカラー(青・緑・オレンジなど)を使用し、アクションを促しましょう。
② 外部予約システムとの連携で、受付の手間を削減
多くの耳鼻科では以下のような外部予約システムが利用されています:
- デジスマ診療(LINE 予約・電子問診連携)
- ドクターキューブ
- EPARK(集患+予約)
- メディカル革命
- LINE 公式アカウント ×Google カレンダー連携
これらのシステムはホームページとボタン・バナー・リンクで連携させるだけで導入でき、24 時間受付・自動リマインド・予約状況の可視化など、多くの利点があります。
③ 「電話予約」も迷わずできるように
一部の年配の患者さんは WEB 予約より電話予約を希望する傾向があります。
- 電話番号はスマホでタップするだけで発信できるようにする(
tel:リンク) - 「お急ぎの方はこちらからお電話ください」など、補足文をつけて安心感を与える
- 診療時間のすぐ下やヘッダーに掲載するのがベスト
④ お問い合わせフォームは最小限&シンプルに
メールフォームも備えておくと、患者や求職者・業者からの連絡にも対応しやすくなります。
ただし、入力項目は多すぎないよう注意しましょう。
- お名前(任意でも可)
- メールアドレス
- お問い合わせ内容
- 診療に関する質問 or 採用に関する質問などのカテゴリ分けがあるとベター
⑤ 「患者さんの行動心理」に沿った導線設計を意識する
患者さんは、ホームページを訪れてから以下のような流れで判断を進めます:
- 自分の症状に対応しているか?
- 医院の雰囲気はどうか?(写真・院長プロフィールなど)
- アクセスしやすいか?(地図・駐車場)
- 予約の仕方は簡単か?(スマホで完結できる?)
これらの流れに沿ってページを設計し、各ステップに「予約ボタン」や「問い合わせリンク」を配置することで、行動を自然に促すことができます。
行きたいと思った“その瞬間”を逃さない
「予約したいと思ったけど、方法が分からず離脱した」
そんな患者さんを一人でも減らすために、常に“次の行動”を促すボタンやリンクを準備しておくことが大切です。
予約への導線は、ただ置くだけでなく、“どこに・どう見せるか”が結果を大きく左右します。
耳鼻科ホームページ制作にかかる費用相場と内訳
「ホームページを作りたいけど、いくらかかるのか分からない」
耳鼻科開業時には医療機器・内装・人件費など多くの初期投資が必要な中、ホームページの費用も慎重に検討すべきポイントです。
ここでは、耳鼻科クリニックのホームページ制作にかかる一般的な費用相場と、依頼方法ごとの内訳や特徴をわかりやすく解説します。
① 費用の相場感(全体イメージ)
| 制作規模 | 参考価格帯 |
|---|---|
| シンプルな LP(1 ページ完結) | 約 5 万円〜15 万円 |
| 5〜6 ページ構成の標準的なサイト | 約 20 万円〜50 万円 |
| デザインカスタム+予約導線付き | 約 30 万円〜80 万円 |
| WordPress 構築+ブログ機能付き | 約 40 万円〜100 万円 |
| 高度なアニメーションや SEO 強化 | 80 万円以上のケースもあり |
② 制作費の内訳項目(何にお金がかかるのか?)
- 構成・ワイヤーフレーム設計費(要件整理・ページ構成)
- デザイン費(トップページ+下層ページの UI デザイン)
- コーディング・開発費(HTML / CSS / JavaScript または Next.js / WordPress など)
- スマホ対応費(レスポンシブ設計)
- お問い合わせフォーム / 外部予約連携の実装
- ドメイン・サーバー設定代行(必要に応じて)
- SEO 内部対策・構造化マークアップ
- 画像選定・文章作成支援(ライティング代行)
③ 依頼先による費用の違いと特徴
| 依頼先 | 特徴 | 費用感 |
|---|---|---|
| 自作(ノーコードツール等) | 費用を最小限に抑えられるが、時間と学習が必要 | 数千円〜数万円 |
| フリーランス | 柔軟な対応が可能だが品質はピンキリ | 10〜30 万円が中心 |
| 制作会社 | デザイン・導線設計・運用サポートまで一貫対応 | 30〜100 万円前後 |
| コンサル+技術者のハイブリッド型(例:弊社) | 戦略設計+制作までを一気通貫で対応 | 20 万円〜要相談 |
④ 月額費用・ランニングコストは?
- ドメイン代:年間 1,000 円〜2,000 円程度(.com / .jp など)
- サーバー代:月額 500 円〜2,500 円程度(X サーバーなど)
- WordPress 保守費:月額 5,000 円〜(依頼する場合)
- 外部予約システム利用料:無料〜月額 5,000 円前後(プランによる)
※当社では、ホームページ開設後も継続した運用サポートが可能です。
⑤ 初期費用だけで判断せず「成果の出るサイト」に投資を
費用だけを重視すると、後々こんな問題が起きることも:
- 「デザインが古臭くて見てもらえない」
- 「スマホで見づらくて離脱される」
- 「SEO が弱くて検索に出てこない」
- 「自分で更新できず、情報が古くなる」
大切なのは“安く作ること”ではなく、“成果につながる投資”にすることです。
そのためにも、医院の特徴・診療方針・立地に合ったホームページ設計が不可欠です。
適正価格で信頼できるパートナーを選ぼう
ホームページは、開業後も長く患者さんとの接点になる“資産”です。
費用の相場を把握したうえで、価格だけでなく「相談しやすさ」「提案力」「運用のしやすさ」まで含めて依頼先を選ぶことが、満足度の高い制作につながります。
よくある失敗パターンと対策
「ホームページはあるのに、なぜか患者が増えない」
そんな悩みを抱えている耳鼻科クリニックは少なくありません。
原因の多くは、“作ったこと”で満足してしまい、集患につながる仕組みが不十分なまま放置されていることです。
ここでは、実際によく見られる失敗パターンと、それぞれに対する具体的な改善策をご紹介します。
① スマホで見づらい・レスポンシブ対応していない
スマホでアクセスした際に、文字が小さい・画像が崩れる・ボタンが押しづらいといった不具合があると、患者はすぐに離脱してしまいます。
改善策:
- モバイルファーストでデザインを設計
- ヘッダーやメニューは固定表示+大きめボタン
- タップ 1 つで電話や予約ができる設計に
② 必要な情報が見つからない・ページ構成が複雑
「診療時間はどこ?」「アクセスがわからない」「予約ボタンが埋もれている」など、患者が求めている情報がすぐに見つからないと、離脱につながります。
改善策:
- トップページに診療時間・アクセス・予約ボタンを明示
- 「患者の行動導線」に沿ったページ構成にする
- パンくずリストや固定ナビゲーションで迷わせない
③ 院長や院内の写真がなく、安心感に欠ける
医療機関では特に、**「どんな先生が診てくれるか」「院内の雰囲気は清潔か」**といった感情的な要素が患者の判断材料になります。
写真が一切ないホームページは、無機質で信頼しにくい印象を与えてしまいます。
改善策:
- 院長の写真付きプロフィール(笑顔・白衣がおすすめ)
- 院内の清潔感ある写真を複数掲載
- スタッフ紹介や Q&A で人間味を伝える
④ 更新されておらず「放置されている印象」がある
お知らせ欄が「〇年前の年末年始の案内」で止まっていると、患者に不安や古さを感じさせてしまいます。
改善策:
- 月 1 回でもよいのでお知らせや季節コンテンツを更新
- ブログ形式で花粉症・インフルエンザ情報などを発信
- WordPress や簡易 CMS で「誰でも更新できる仕組み」を整備
⑤ 外部予約システムが連携されていない・誘導が弱い
せっかく予約機能があるのに、「どこから予約すればいいか分からない」
これは非常にもったいない状態です。
改善策:
- 常に見える位置に予約ボタンを設置(スマホ右下など)
- ボタンは目立つ色にし、アニメーションなどで視線誘導
- 外部システム(デジスマ・ドクターキューブ等)との連携確認
⑥ SEO 対策がされておらず検索に出てこない
「耳鼻科 ○○ 駅」で検索しても公式サイトが表示されない場合、検索対策(SEO)がまったくされていない可能性があります。
改善策:
- タイトルやメタディスクリプションを最適化
- h1〜h3 タグを使った見出し構成を整備
- Google ビジネスプロフィールにリンク・情報を登録
ホームページは「育てる」もの
ホームページは作って終わりではなく、使いやすさ・分かりやすさ・信頼感を継続的に改善していくべき資産です。
本記事で紹介したチェックポイントをもとに、自院のサイトが“選ばれる理由”をしっかりと伝えられているか、ぜひ確認してみてください。
耳鼻科のホームページ公開後にやるべきこと
ホームページは「作って終わり」ではありません。
公開してからが本当のスタートです。
特に耳鼻科クリニックのような地域密着型の医療機関では、継続的な情報発信とメンテナンスが“集患力”を左右します。
ここでは、ホームページ公開後に必ず行いたい施策を「更新・SEO・集患」の観点からご紹介します。
① 定期的なお知らせ更新(医院からの“声かけ”)
- 休診案内
- インフルエンザ・花粉症シーズン到来のお知らせ
- 新しい機器の導入
- スタッフの募集や体制変更
これらは小さなことでも構いません。
定期的な更新があることで、「きちんと運用されているサイト」=信頼できる医院という印象につながります。
ポイント:
- 月に 1 回の更新を目安にする
- WordPress や簡易 CMS でスタッフが簡単に投稿できる仕組みを整える
- 最新情報がトップページに自動で表示される構成にする
② Google ビジネスプロフィール(旧:Google マイビジネス)の整備
Google 検索や Google マップで最も多く表示されるのが**「ビジネスプロフィール(MAP 枠)」**です。
対応するべき項目:
- 診療時間・電話番号・公式 URL
- 院内写真・院長写真
- 診療メニュー(耳・鼻・喉など分かりやすく記載)
- 口コミへの返信
口コミは医院選びの決定打になるケースも多く、対策必須です。
③ 院内掲示・印刷物・SNS からの連携導線
- チラシや診察券に QR コードを記載
- 院内ポスターに「WEB 予約はこちら」
- LINE 公式アカウントや Instagram との連携も検討可
これにより、リアルから WEB への自然な導線が生まれ、患者との接点が広がります。
④ SEO 対策の基本(地域+診療名で検索される構造に)
耳鼻科は「〇〇駅 耳鼻科」「〇〇市 花粉症」など、地域+症状名での検索が中心です。
これを意識して、サイト内のテキストやページ構成を見直しましょう。
対応すべき SEO の基本項目:
- 各ページに適切なタイトル・メタディスクリプションを設定
- h1〜h3 見出しタグを階層的に構成
- 「耳鼻科」「花粉症」「めまい」など具体的な症状ワードを散りばめる
- 画像には alt テキスト(代替テキスト)を設定
⑤ ブログ・季節コンテンツで“検索流入”を増やす
Google は「更新頻度」や「有益な情報」を高く評価します。
以下のような記事を定期的に発信することで、SEO 効果と専門性の両方を強化できます。
- 「今年の花粉はいつから?」「花粉症対策とおすすめ治療法」
- 「お子さまの耳垢掃除、どうすればいい?」
- 「夏の耳トラブル|プール後の外耳炎に注意」
患者さんの疑問を解消しながら、検索流入を増やす入口にもなります。
ホームページは“育てる”ことで資産になる
開業と同時に立ち上げたホームページも、定期的な情報更新と SEO 意識のある運用を続けることで「集患力を持つ資産」に成長していきます。
「作って終わり」ではなく、「育てながら成果を出す」ホームページ運用を心がけましょう。
耳鼻科ホームページは誰に依頼するかが成果を左右する
ホームページは“医院の顔”です。
デザインだけでなく、集患・信頼感・検索対策・予約導線など、クリニック経営に直結する要素が詰まっています。
そのため、「誰に制作を依頼するか」は、サイトのクオリティだけでなく“ビジネスの成果”にも大きく影響します。
① 「安いから」「知り合いだから」で選ぶのは危険
ホームページ制作は価格もピンキリ。
つい「安さ」や「気軽さ」で依頼先を決めてしまいがちですが、以下のような失敗につながるケースもあります。
- デザインは綺麗でも、予約や SEO 導線が考慮されていない
- 納品後の修正や更新対応に一切応じてもらえない
- 医療業界の知識がなく、必要な情報が抜けている
- スマホ非対応、保守管理が不明確
失敗例:
開業前に急いで依頼したが、開院当日にサイトが間に合わなかった
文字ばかりのホームページで離脱率が高く、集患につながらなかった
修正のたびに高額な費用が発生して困った
② 医療・クリニック制作に慣れている制作者を選ぶ
耳鼻科を含む医療機関のホームページでは、一般サイトとは異なる配慮や構成が必要です。
例:
- 予約・混雑対策など患者導線の最適化
- 医療広告ガイドラインの遵守(虚偽表現の回避)
- 高齢者でも見やすい UI 設計
- 院内写真の掲載方針や顔出しへの配慮
これらを理解している制作者に依頼することで、医院側の手間も減り、成果の出やすいホームページになります。
③ 「制作だけ」でなく「設計・運用まで」相談できるパートナーを
おすすめは、“コンサル+技術”の両方を兼ね備えたパートナーに依頼することです。
✔︎ 何を載せるべきかを整理してくれる
✔︎ ターゲットや地域性に合わせた導線を設計してくれる
✔︎ 公開後も更新や SEO について相談できる
このような制作者であれば、単なる Web 制作ではなく“医院経営の味方”として長く付き合える存在になります。
④ 当社(KUBOYA)の強み
弊社では、中小企業診断士 × ソフトウェアエンジニアとしての知見を活かし、「見た目のデザイン」だけでなく「成果につながる構成・導線・戦略」を重視したサイト制作を行っています。
- 開業準備段階からヒアリング可能
- スマホ最適化・SEO・予約導線までワンストップ対応
- 医療機関・地域ビジネスに特化したサイト設計
- 制作後の運用支援・保守管理・改修も柔軟に対応
「まだ何も決まっていない…」という段階でも大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください。
技術だけでなく「信頼と提案力」で選ぶべき
ホームページ制作は、単なる外注ではなく医院のブランディングを一緒に作り上げるパートナー選びです。
誰に頼むかで、集患数・患者の第一印象・運用のしやすさが大きく変わります。
ぜひ信頼できる制作者とともに、成果につながる耳鼻科ホームページをつくっていきましょう。
📘 続けて読みたい関連記事
👉 【2025 年版】内科クリニックのホームページ制作ガイド|信頼される構成と費用相場とは?
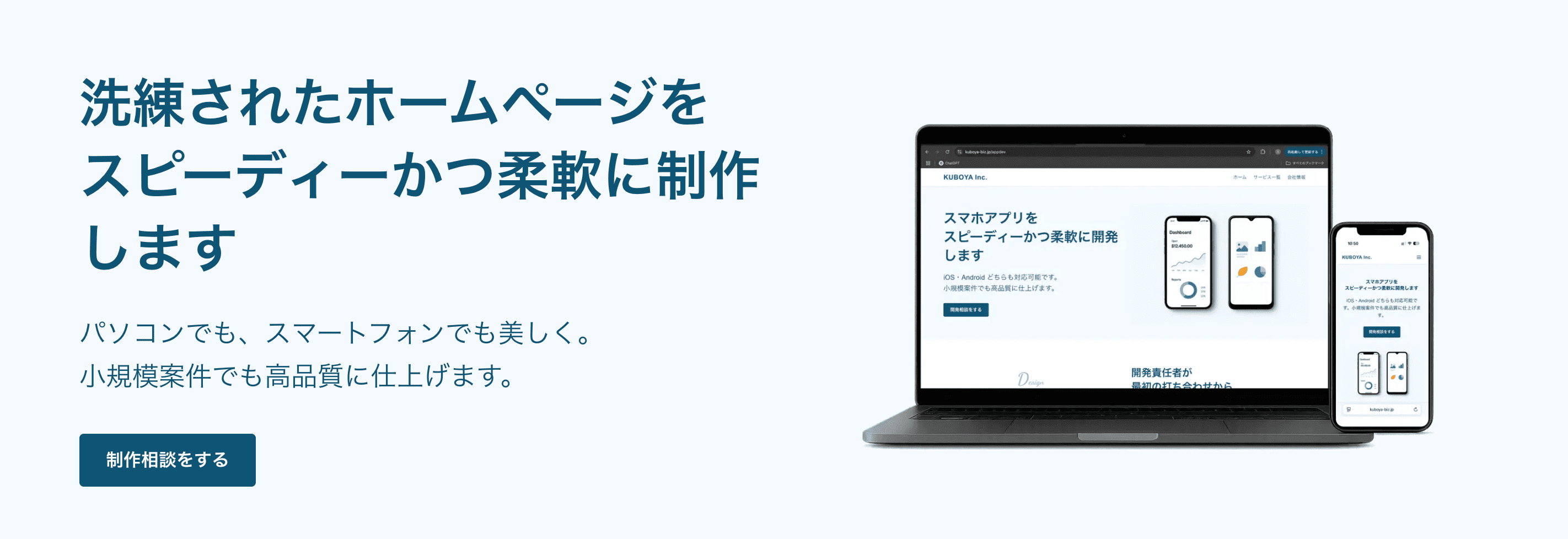 👉
👉