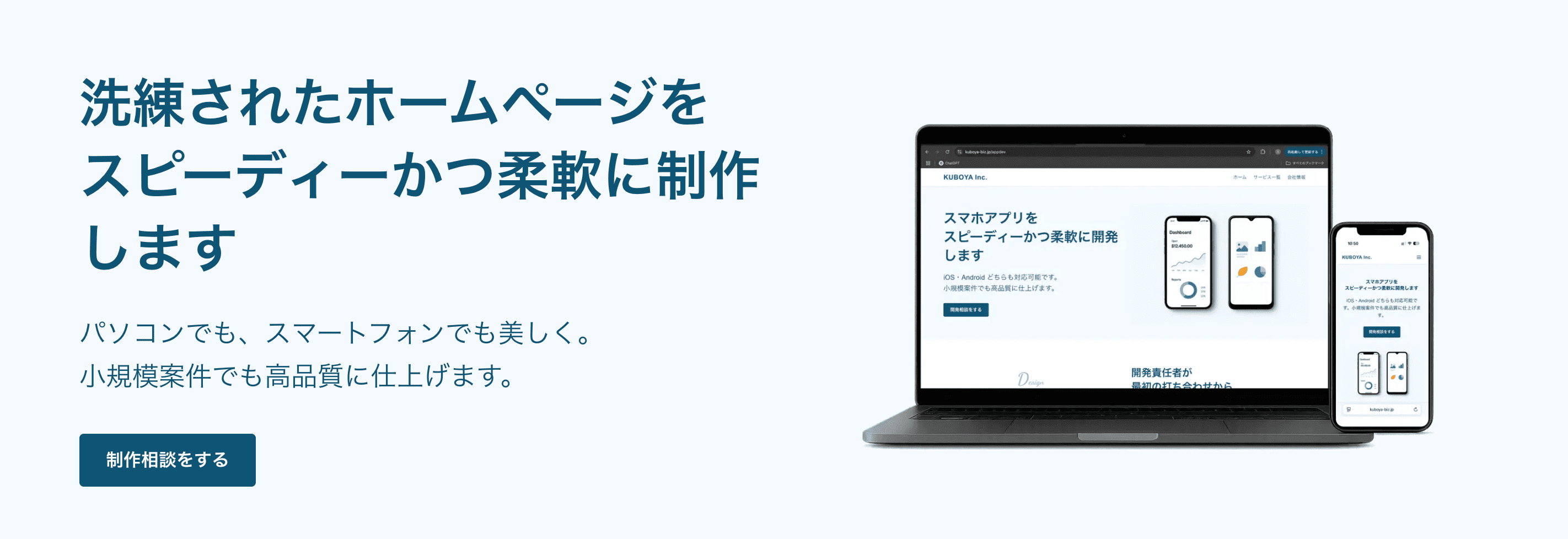【開業準備】行政書士のホームページ制作ガイド|集客につながる5つのポイント
2025-05-28
監修:久保谷 太志
経済産業大臣認定 中小企業診断士 / Web制作ディレクター
目次

✅ 行政書士のホームページ制作なら、【株式会社 KUBOYA】にお気軽にご相談ください。
なぜ行政書士にホームページが必要なのか
行政書士として開業・独立を考えたとき、「どこに事務所を構えるか」「どんな業務を主軸にするか」と並んで、必ず検討すべきなのがホームページの開設です。
特に近年は、知人からの紹介や地元の繋がりだけではなく、Google 検索やスマホ経由でサービスを探す顧客が急増しています。
行政書士のように、法律に関わる専門性の高い業種では、信頼感と専門性が第一印象で判断されるため、ホームページの有無やその内容が、依頼に繋がるかどうかを大きく左右します。
行政書士のホームページが果たす 3 つの役割
1. 信頼構築(信用を得る)
行政書士という業種は、一般の人からすると「誰に頼めばいいか分からない」サービスです。
実績・プロフィール・保有資格・対応地域などがしっかり記載されたページがあるだけで、「この人に任せても大丈夫そう」という心理的安心を与えることができます。
2. 集客(新規顧客を獲得)
多くの依頼者は、まず「行政書士+地域名」で検索します。
その際、検索結果に表示されたサイトがしっかりしていれば、「問い合わせ → 面談 → 依頼」という流れに繋がる確率が高くなります。
特に、相続・許認可・契約書作成など、特化した業務内容を明示しておくことで、ニーズの合致率が高まります。
3. 差別化(他事務所との違いを出す)
競合の行政書士も多数いるなかで、ホームページは自分の特徴や方針を伝える場になります。
例えば、「地域密着で迅速対応」「LINE で相談可能」「建設業許可に特化」など、ターゲットに響く要素を打ち出すことで、選ばれる理由をつくることができます。
依頼者がホームページを見ている具体的なポイント
行政書士に業務を依頼しようと考える人が、ホームページで見ているのは以下のような要素です。
- 対応業務(何ができるのか)
- 料金(目安でもいいので明記)
- 実績(経験年数・事例)
- 代表者プロフィール(顔・経歴・メッセージ)
- 問い合わせ方法(電話・メール・LINE など)
このような項目が適切に整理されているだけで、“問い合わせしやすい事務所”として印象付けることができます。
経験者の声:「ホームページがあると紹介が増える」
実際に行政書士として開業された方の中には、「名刺に URL を載せることで信頼感が増した」「紹介された人がまずホームページを見て、安心して連絡してくれた」という声も多く聞かれます。
ホームページは、あなたの事務所の“営業担当”として、24 時間 365 日働いてくれる存在です。
今後さらに重要になる「検索からの流入」
スマートフォンの普及により、地域密着型の士業でも「ネットで調べてから相談」が一般的になっています。
これは特に、相続や離婚、外国人ビザ、遺言書作成など、人生の中で何度も経験しない悩みに関しては、第三者に相談する前に、まずネットで調べる傾向が強いからです。
つまり、ホームページを作ることは「これから出会う顧客との入り口」を作ることであり、**開業後に必要な集客活動の“基礎インフラ”**と言っても過言ではありません。
このように、行政書士にとってホームページは単なる名刺代わりではなく、「信頼の証」「集客装置」「差別化ツール」として欠かせない存在なのです。
行政書士ホームページの役割とは
行政書士の業務は「相談を受けて書類を作成する」だけにとどまらず、依頼者の人生に関わる重要な局面を支える仕事です。
そんな責任ある業務を担う行政書士にとって、ホームページは単なる“案内板”ではなく、ビジネスの中心的なツールとして活用すべき存在です。
この章では、行政書士のホームページが果たす 2 つの大きな役割 ──「信頼構築」と「集客」── について、具体例を交えて解説します。
信頼構築|初対面でも安心感を与える仕組み
現代の依頼者の多くは、実際に連絡を取る前に、必ずホームページを確認します。
このときに感じる「雰囲気」「信頼感」「誠実さ」が、最初の“選ばれる・選ばれない”の分かれ目になります。
▶ 具体的な信頼要素
- 代表者の顔写真とあいさつ文
- 登録番号・所属会・保有資格の明記
- 過去の対応実績やお客様の声
- 料金目安の明確化(曖昧にしない)
- 専門分野や得意な業務の明示
これらの情報が整理されているだけで、「よくわからない士業」から「相談できそうな専門家」に変化します。
▶ 逆に不信感を与えるケース
- 古いデザインやスマホ未対応のサイト
- 顔・事務所所在地・プロフィールがない
- 業務内容が曖昧、更新日が何年も前
ホームページを放置している事務所は、依頼者から「この事務所、ちゃんと稼働しているの?」と思われてしまうリスクがあります。
集客|ネット検索からの自然流入を獲得する
行政書士への依頼は、比較的“突発的”なニーズが多いのが特徴です。
たとえば:
- 「相続手続きで困っている」
- 「離婚協議書を作りたい」
- 「建設業許可を取りたい」
こうした人の多くは、まずスマホで「行政書士 相続 ○○ 市」などと検索します。
ここで、あなたのホームページが上位に表示されていれば、自然にアクセスが集まり、「問い合わせ」や「面談予約」に繋がります。
これがいわゆる “検索流入による集客” です。
▶ 検索集客のメリット
- 営業せずとも自動でアクセスが増える
- 「今すぐ依頼したい人」が来る可能性が高い
- 競合より上に表示されれば圧倒的有利
▶ 成功のカギは「キーワード選定」
単に「行政書士」と書いてあるだけでは埋もれてしまいます。
地域名や業務特化キーワードを組み合わせて、「検索される言葉」でページを作ることが重要です。
例:
- 「行政書士 相続サポート 横浜」
- 「ビザ申請 行政書士 外国人対応可 千葉」
信頼と集客は両立できる
一見、「信頼感のあるデザイン」と「SEO で上位に出す構成」は別の話に見えますが、実はどちらも同じ方向性で設計することが可能です。
例えば:
- 検索されやすいキーワードを見出しに使いながら
- ページ全体は丁寧で読みやすく、安心感あるレイアウトに仕上げる
このように設計されたホームページは、「アクセスはあるけど問い合わせがない」というよくある失敗を回避し、“見られる → 信頼される → 問い合わせが来る”という理想の流れを実現します。
結論|ホームページは営業と接客を同時にこなす「最強のスタッフ」
行政書士として独立した直後は、営業活動や認知拡大に頭を悩ませることが多いと思います。
しかし、しっかり設計されたホームページは、**24 時間 365 日、あなたの代わりに営業・接客・信用づくりを担ってくれる“最強のスタッフ”**になります。
単なる名刺代わりではなく、「信頼と集客を両立させるツール」として、しっかり投資する価値があるといえるでしょう。
制作前に考えるべき 3 つのこと
行政書士としてホームページを制作する際、いきなりデザインや文章から着手してしまうのは NG です。
その前に、**「誰に・何を・どうやって伝えるか」**という根本的な戦略を明確にする必要があります。
ここが曖昧なまま作ってしまうと、「内容はあるけど誰にも響かない」「アクセスはあるが問い合わせが来ない」ホームページになりがちです。
この章では、制作前に必ず整理しておくべき 3 つの軸を具体的に解説します。
1. ターゲット|誰に向けて発信するかを明確にする
行政書士の業務は非常に幅広く、相続・遺言・会社設立・外国人ビザ・建設業許可・農地転用など多岐に渡ります。
すべてを一度にアピールするのではなく、まずは**「自分がメインで取りたい依頼」=コアターゲット**を定めましょう。
▶ 具体例
- 「中小企業経営者向けの許認可サポート」
- 「高齢者向けの相続・遺言相談」
- 「在留資格に悩む外国人と企業支援」
これにより、サイトの文章やデザインもその層に合わせた「言葉遣い」「写真選び」「情報構成」が可能になります。
▶ ターゲットが曖昧だと?
- 内容が広く浅くなり、誰の心にも刺さらない
- 競合との差別化ができない
- 問い合わせの“質”がばらつく
2. サービス|自分が何を提供できるのかを整理する
次に考えるべきは、「自分が何を提供しているのか」というサービスの棚卸しです。
行政書士業務は、依頼者にとって非常にわかりづらい領域なので、専門用語を噛み砕いて説明できるかどうかが大事です。
▶ 明確にすべきこと
- 対応できる業務とその流れ(例:建設業許可の申請手順)
- 提供範囲(書類作成のみ/行政とのやりとり代行も含む 等)
- 費用の目安(相場感だけでも掲載すると安心感アップ)
- サポートの特徴(迅速対応、オンライン相談対応、LINE で完結 など)
依頼者は「何をやってくれるのか」がわからないと、問い合わせまで踏み切れません。
ホームページ上で、サービス内容を具体的・わかりやすく提示することが信頼構築につながります。
3. 差別化|なぜ自分が選ばれるべきかを考える
最後に重要なのが「差別化」です。
現在、行政書士は全国に約 5 万人以上。
特に都市部では同業者が多数存在するため、“他の事務所と何が違うのか”を明確に伝えることが重要です。
▶ 差別化の切り口(例)
- ○○ 業界出身の行政書士による専門対応
- 地域密着で土日・夜間も対応可能
- 相談から書類作成まで LINE だけで完結
- ○○ 市で唯一、○○ 分野に特化した事務所
▶ よくある NG パターン
- 「誠実に対応します」「お客様第一主義」など抽象的な言葉だけ
- 競合と見た目・内容がほぼ同じ
- 自分の強みを言語化できていない
差別化は、単に“変わったこと”をするのではなく、「この人に頼みたい」と思わせる納得感あるストーリーが必要です。
そのためにも、実績・人柄・専門分野を軸に、自分の強みを洗い出しておきましょう。
制作前の「設計図」が成否を分ける
ホームページ制作は、家づくりと同じで、設計図なしでは完成度が低くなります。
「ターゲットは誰か」「どんなサービスを見せるか」「どうやって選ばれるか」── この 3 点を明確にしてから制作を始めることで、集客力と信頼性を兼ね備えたホームページが完成します。
まずは、紙とペンを使ってでも構いません。
ご自身の業務内容・得意分野・理想の依頼者像を言語化してみることから始めてみましょう。
✅ 行政書士のホームページ制作なら、【株式会社 KUBOYA】にお気軽にご相談ください。
ホームページに掲載すべき必須コンテンツとは
行政書士として信頼を獲得し、依頼につなげるホームページを作るには、「何を載せるか」が成功のカギになります。
ただなんとなくプロフィールと業務一覧を載せただけでは、訪問者にとって「また同じような士業サイトだな」という印象になってしまい、差別化もできません。
この章では、集客につながる行政書士ホームページに必須のコンテンツ 8 つと、それぞれにおけるポイントを詳しく解説します。
1. トップページ|第一印象を決める最重要エリア
トップページは、まさにホームページの「顔」。
訪問者の 8 割はまずここをざっと見て、1〜3 秒で「このサイトは信頼できそうか?」を判断します。
▶ トップページで伝えるべきこと
- 提供するサービスの概要(相続、許認可、ビザなど)
- 対象となるエリア(地域名)
- あなたの強み(専門性や対応姿勢)
- 問い合わせ導線(目立つ場所にボタンや電話番号)
▶ ファーストビューに「誰が・何を・誰向けに」やっているかを端的に出すことが重要です。
2. 代表プロフィール|人となりが伝わる紹介文
行政書士は“人”で選ばれる職業です。
そのため、プロフィールページは非常に重要なコンテンツとなります。
▶ 書くべき情報
- 氏名・顔写真(できれば自然な表情のもの)
- 経歴・行政書士になったきっかけ
- 専門分野やポリシー
- 趣味や人柄が分かる要素
▶ 形式的ではなく、「この人に相談したい」と思わせる温かさや誠実さが伝わる内容を心がけましょう。
3. サービス内容(業務案内)
あなたが対応できる業務を、専門用語をできるだけ避けて丁寧に解説しましょう。
ここが曖昧だと、「何が頼めるのか分からない」という状態になってしまいます。
▶ 表現のコツ
- 「相続手続き」「建設業許可申請」など、検索されやすい言葉を見出しに使う
- 対応できる範囲・流れ・納期・費用の目安などを記載
- よくある質問(Q&A)を添えると安心感アップ
4. 料金表(費用案内)
士業の世界では、費用が明確でないことが不安材料になりやすいです。
実際に「料金が書かれていないから問い合わせしにくかった」という声も多く聞かれます。
▶ ポイント
- 初回相談無料 or 有料の明記
- 基本料金の目安(「〜円〜」「業務内容により異なります」でも OK)
- オプション料金や交通費などの補足
▶ 不安を減らすために、可能な範囲で“料金感”を伝えることが大切です。
5. お客様の声(実績紹介)
実際に依頼された方の声は、何よりの信頼材料です。
「どんな人が、どんな理由で、どんな効果があったか」を具体的に伝えましょう。
▶ 掲載の工夫
- 性別・年代・職業(実名は不要でもリアリティを)
- 対応内容・満足ポイント・解決した悩み
- 直筆アンケートの写真や動画もあれば効果大
▶ 「自分と似た状況の人が依頼して満足している」というストーリーは、強力な安心感を生みます。
6. よくある質問(FAQ)
訪問者がホームページを見ながら不安に思うことを事前に解消できるページが FAQ です。
▶ よくある質問の例
- 「相談だけでもできますか?」
- 「土日や夜間も対応可能ですか?」
- 「急ぎの依頼にも対応できますか?」
- 「どんな書類を用意すればよいですか?」
▶ 問い合わせのハードルを下げる効果があり、コンバージョン率アップに直結します。
7. 事務所案内・アクセス情報
リアルな事務所の存在感を出すことも大事です。
Google マップの埋め込みや、外観写真などを掲載すると安心感が高まります。
▶ 掲載すべき情報
- 住所(建物名・階数まで正確に)
- 最寄り駅や駐車場情報
- 電話番号・FAX
- 営業時間・定休日
▶ 地域密着型なら、「○○ 駅徒歩 3 分」「○○ 市役所から車で 5 分」など、地元目線の説明が効果的です。
8. お問い合わせページ
最後に、もっとも重要なのが「問い合わせ導線」です。
どんなに内容が良くても、連絡しにくければ依頼にはつながりません。
▶ 問い合わせページに必要な要素
- メールフォーム(スマホ対応)
- 電話番号(時間帯の記載も)
- LINE やチャット対応がある場合は明記
- プライバシーポリシーや個人情報の取り扱いへの配慮
▶ 「まずは相談だけでも大丈夫です」といった安心文言も効果的です。
必須コンテンツが揃えば“信頼と行動”が生まれる
ホームページは情報の集合体ではありません。
目的は「信頼を得て、行動してもらう」こと。
今回ご紹介した 8 つのコンテンツを適切に設置し、訪問者の不安や疑問に先回りして答えることで、問い合わせにつながる強いサイトを作ることができます。
集客につながるデザインと構成のポイント 5 選
行政書士としてのホームページにおいて、文章やコンテンツと同じくらい重要なのが「デザイン」と「構成」です。
いくら中身が充実していても、見づらく古臭いデザインでは信頼感を損ね、問い合わせに繋がる前に離脱されてしまうリスクがあります。
ここでは、行政書士ホームページを集客ツールとして機能させるための、具体的なデザイン・構成のポイントを 5 つに絞って解説します。
1. スマホ最適化(モバイルファースト)
現在、士業のホームページ訪問者の6〜7 割以上がスマートフォンからアクセスしています。
そのため、パソコン画面を前提とした古いデザインでは、スマホでの閲覧時に文字が小さすぎたり、操作しづらくなったりして、すぐに離脱されてしまいます。
▶ 対応のチェックポイント
- スマホ画面で見たときに文字が読みやすいか
- ボタンが押しやすい位置・大きさか
- メニューがスライドで展開されるか(ハンバーガーメニュー)
▶ **スマホで快適に読めることが、“第一の信頼”**につながります。
2. ファーストビューで安心感を与える
「ファーストビュー」とは、ページを開いた瞬間に画面に表示される最初のエリアのこと。
この数秒間の印象で、「ここなら相談しても大丈夫そう」と思ってもらえるかどうかが決まります。
▶ ファーストビューに入れるべき要素
- 「行政書士 ○○」と明示(職種と専門性)
- サービスの簡潔な紹介文(例:相続・遺言・許認可)
- 顔写真や事務所の外観写真(安心感)
- 問い合わせボタン(目立つ色で)
▶ 「誰が・何を・誰に向けて」やっているかを、視覚と文字で一瞬で伝えることが大切です。
3. 強調すべき情報の視覚的工夫
ホームページに載せる情報は多くなりがちですが、すべてを同じトーン・同じ書き方で表示してしまうと、大事な情報が埋もれてしまいます。
▶ 見せ方の工夫例
- 問い合わせボタンは目立つ色+固定表示で常にアクセスできるように
- 料金・対応業務は表やアイコンで分かりやすく
- 「選ばれる理由」や「他事務所との違い」は囲み枠やイラストを使って強調
▶ 視線の流れを設計することで、問い合わせ導線への自然な誘導が可能になります。
4. 色・フォント・写真の統一感
見た目の「安心感」は、色や書体、写真の使い方によっても大きく左右されます。
バラバラなフォントや色を使うと、雑多で素人っぽい印象を与えてしまいます。
▶ デザイン統一のコツ
- 基本の色は 2〜3 色に抑える(例:ネイビー+白+アクセントにゴールドなど)
- フォントは 1〜2 種類に絞る(明朝体+ゴシック体など)
- 写真は明るく清潔感のあるものを選定(できればプロカメラマン)
▶ 一貫性のあるデザインは、無意識のうちに「ちゃんとしている事務所だ」という印象を与えます。
5. CTA(問い合わせ導線)の配置と数
CTA(Call To Action)とは、「問い合わせはこちら」など、行動を促すパーツのこと。
これがない、もしくは 1 箇所しかないサイトは、どれだけアクセスがあっても**“取りこぼし”が発生します。**
▶ CTA の配置ポイント
- 各ページ下部にフォームまたはボタンを設置
- スマホでは画面下部に「固定ボタン」で常時表示
- 「今すぐ相談する」など明確なアクションを促す文言にする
- 相談のハードルを下げる文言(例:「まずは無料相談から」)
▶ CTA は**「問い合わせへの背中を押す最後の一手」**です。控えめにせず、しっかり目立たせましょう。
デザインは「センス」より「設計」
デザインと聞くと、特別なセンスが必要なように思われるかもしれませんが、実際はそうではありません。
行政書士ホームページに求められるのは、派手さではなく、信頼・見やすさ・わかりやすさです。
今回ご紹介した 5 つのポイントを押さえれば、誰でも「集客につながる設計」が可能です。
ホームページは、ただ“ある”だけでは意味がありません。
「見た人が安心して問い合わせしたくなる構造」を意識して作ることこそが、成果を生むサイトの条件です。
行政書士におすすめの制作方法を比較
ホームページを作ろうと決めたとき、多くの行政書士が最初に悩むのが「自分で作るべきか、それとも業者に依頼するべきか」という点です。
どちらにもメリット・デメリットがあり、予算・目的・スキルによって最適な選択は異なります。
この章では、自作と外注のそれぞれの特徴、適したケース、注意点を詳しく比較し、行政書士にとって最適な選択を導き出します。
自作する方法と特徴
▶ 方法例
- WordPress(テンプレート使用)
- Wix / Jimdo / STUDIO などのノーコードツール
- HTML + CSS の手書き(技術がある方向け)
▶ メリット
- 初期費用が安い〜無料で始められる
- 納得いくまで自分のペースで作れる
- サイト更新が自由自在(都度の費用不要)
▶ デメリット
- デザイン・構成・SEO などに知識が必要
- 時間がかかり、業務と両立しづらい
- 集客につながるクオリティに届かないことも
▶ 自作が向いている人
- IT リテラシーがあり、学ぶことに抵抗がない
- 時間的に余裕がある(開業準備中など)
- 最低限の名刺代わりページがあればいい
外注する方法と特徴
▶ 方法例
- ホームページ制作会社
- フリーランスの Web デザイナー
- 士業特化型の制作サービス(行政書士専用など)
▶ メリット
- プロによる設計・デザインで信頼感アップ
- スマホ対応・SEO 対策などもカバーされる
- 公開までのスピードが早い(1〜2 ヶ月程度)
▶ デメリット
- 初期費用がかかる(相場:5〜30 万円程度)
- 月額費用や更新依頼にコストがかかる場合も
- 制作会社選びに失敗すると満足度が低い
▶ 外注が向いている人
- 集客や信頼構築を本格的に狙いたい
- デザインや技術に自信がない
- 自作に時間をかけるより業務に集中したい
自作と外注の比較表
| 比較項目 | 自作 | 外注 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 無料〜数千円 | 数万〜数十万円 |
| 月額費用 | 無料〜サーバー代程度 | 制作会社によっては発生 |
| 制作スピード | 自分次第 | 通常 1〜2 ヶ月程度 |
| クオリティ | 自分のスキルに依存 | プロ品質で安心感がある |
| 自由度 | 高い | 制作後は一部制限がある場合も |
| 集客力 | 工夫次第で可 | SEO 設計も含めて強い |
行政書士におすすめの選び方
もしあなたが開業したばかりで、**「まずは最低限のページがあればいい」「とにかく予算を抑えたい」**という段階であれば、STUDIO や Wix などのノーコードツールで名刺代わりのページを作るのも良い選択です。
一方で、しっかりした見た目で信頼感を出したい、検索からの集客も狙いたい、時間がないのでプロに任せたいという場合は、外注がおすすめです。
特に、士業特化型の制作会社や、行政書士の案件実績があるフリーランスを選ぶと、業務理解があるためスムーズに進められます。
注意点|外注時は「制作後のサポート」も確認
外注する場合、制作だけでなく「公開後の保守や更新」についても事前に確認することが重要です。
- 月額保守費はかかるか?
- 自分で更新できる管理画面があるか?
- テキスト修正や画像変更の費用感は?
「作って終わり」ではなく、長く運用していけるかどうかを基準に選びましょう。
まとめ:時間を取るか、お金を取るか
ホームページ制作は、「自分の時間を使う」か「お金で時間を買う」かという選択でもあります。
行政書士としての本業に集中したいなら、プロに任せて、“営業ツールとして成果を出す”ホームページを持つ方が、結果的に費用対効果が高くなるケースも少なくありません。
あなたの今の状況と目的に合わせて、最適な方法を選んでください。
制作費の相場と月額費用の考え方
行政書士としてホームページを持つとき、多くの方が最も気になるのが「いくらかかるのか?」という費用面です。
しかし、ホームページ制作の価格は非常に幅広く、5 万円程度の格安プランから 100 万円を超えるハイエンドプランまで存在します。
ここでは、行政書士がホームページを作る際の「初期費用の相場」「月額費用の内訳」「コストを抑えるポイント」を解説し、“安かろう悪かろう”に陥らないコスパ重視の選び方を紹介します。
初期制作費の相場
▶ おおまかな価格帯
| タイプ | 費用相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自作(Wix/STUDIO 等) | 無料〜3 万円程度 | ドメイン取得や有料テンプレ費用のみ |
| フリーランス | 5 万〜20 万円 | 柔軟な対応・個人対応・納期は長め |
| 制作会社(一般) | 15 万〜50 万円 | サポート充実・デザイン提案あり |
| 士業特化の制作会社 | 20 万〜80 万円 | 業務理解あり・テンプレ活用も可 |
※あくまで目安です。オプションやページ数により増減します。
▶ 価格に影響する要素
- ページ数(1P 構成〜10P 以上)
- オリジナルデザイン or テンプレート活用
- スマホ最適化の有無
- 問い合わせフォームの数
- 写真撮影やライティングの有無
▶ 価格だけで判断するのではなく、「何が含まれているか」を必ず確認しましょう。
月額費用の種類と目安
ホームページは作ったあとも、ドメイン・サーバー管理・保守対応などで継続的な費用が発生します。以下は主な内訳です。
▶ 維持にかかる主な費用
| 項目 | 内容 | 月額目安 |
|---|---|---|
| ドメイン | 例:○○.jp などの取得費 | 100〜500 円 |
| サーバー | Web サイトを表示するためのスペース | 500〜2,000 円 |
| 保守管理 | 定期バックアップ・更新対応など | 3,000〜10,000 円 |
| CMS 利用料 | WordPress や STUDIO などの有料プラン | 0〜3,000 円 |
※制作会社に「月額制」で依頼する場合は、これらが一体化していることも多いです。
▶ よくある落とし穴
- 月額 1 万円以上かかっているが、何をしているか不明
- 自分で更新できないシステムで、都度依頼コストがかかる
- 解約時に「サイトの所有権が業者にある」ケース
▶ 「費用が発生している=サービスを受けられているか」を必ずチェックしてください。
コストパフォーマンス重視で選ぶポイント
費用は重要ですが、価格が安ければいいというわけではありません。
特に行政書士のように「信頼感」が何より大切な業種では、安っぽいデザインや不親切な構成は逆効果になります。
▶ コスパが高いと感じる制作会社の特徴
- 制作内容・対応範囲が明確に提示されている
- 修正や保守の料金体系が分かりやすい
- 実績ページがあり、事例が公開されている
- 初期費用と月額費用の“バランス”が良い
- CMS(更新システム)付きで自分でも修正できる
▶ おすすめの判断基準
- 初期費用:10〜30 万円
- 月額費用:0〜5,000 円
- ページ数:5〜7 ページ程度(TOP・プロフィール・業務内容・料金・FAQ・お問い合わせ)
▶ この価格帯であれば、見栄え・信頼性・維持費のバランスが良く、十分な集客力も期待できます。
“高すぎず、安すぎない”が最適
制作費が高すぎる=コスト回収に時間がかかる
制作費が安すぎる=信頼感が損なわれる
このバランスが最も重要です。
行政書士のホームページは、「信頼感があり、かつ問い合わせに繋がるサイト」こそが投資対効果の高い成功パターンです。
補足:ホームページ制作の助成金・補助金も活用できる場合がある
自治体や商工会議所が実施している創業支援・デジタル化推進の助成制度を活用すれば、制作費の一部〜全額をカバーできる可能性もあります。
例:
- 小規模事業者持続化補助金(最大 50 万円)
- 各市区町村の創業補助制度
▶ 該当する地域・タイミングによって異なるため、早めに確認・申請しておくと非常にお得です。
**費用は“コスト”ではなく“未来への投資”**と捉え、
事務所の信頼力・集客力を高める一歩として、納得できる予算設計を行いましょう。
ホームページの制作後にやるべきこと
ホームページは「作ったら終わり」ではありません。
むしろ公開してからこそ、“運用フェーズ”こそが集客と信頼獲得の本番です。
この章では、行政書士がホームページ公開後に取り組むべき施策を 3 つの柱に絞って解説します。
どれも費用をかけずに始められるものばかりなので、実践すれば着実に効果が現れます。
1. SEO 対策(検索エンジン最適化)
SEO とは、Google などの検索エンジンであなたのホームページが上位表示されやすくなるための取り組みのことです。
▶ 基本の SEO チェックポイント
- 各ページに明確なタイトル(title タグ)があるか
- 見出し(H1〜H3)が論理的に構成されているか
- ページごとに固有の説明文(meta description)が設定されているか
- 「行政書士+業務+地域名」のような検索キーワードを含めているか
- 画像に alt 属性が設定されているか
▶ 行政書士に強いローカル SEO 対策
- 各ページで「○○ 市」「○○ 区」など地名を複数配置
- 地域名を含む業務ページを複数用意(例:「建設業許可 ○○ 市」)
- 「対応エリア」ページを設ける(→ 地域 SEO に効果大)
▶ 小手先のテクニックではなく、「誰の検索に応えるか」を意識した構成にすることが重要です。
2. Google ビジネスプロフィール(旧:Google マイビジネス)の活用
Google で「○○ 市 行政書士」と検索した際に、検索結果の上部に地図と共に表示される事業所情報、それが**Google ビジネスプロフィール(GBP)**です。
▶ 活用方法と効果
- 無料で登録可能
- 営業時間・住所・電話番号・ホームページ URL を掲載
- 「口コミ」欄に依頼者の評価を集められる
- 写真(事務所・本人・資料等)を定期的に投稿できる
▶ 行政書士におけるメリット
- 地域検索での表示率が高まる
- 地図経由で直接ナビや電話ができ、利便性が高い
- 口コミが蓄積されることで信頼性が上がる
▶ 登録していない行政書士事務所も多いため、今からでも大きな差別化ポイントになります。
3. 口コミ・レビュー対策
行政書士業務の性質上、お客様の満足度は“信頼の積み重ね”に直結します。
その信頼の可視化手段が、Google やホームページ上の口コミです。
▶ 口コミを集める方法
- 依頼完了後に丁寧に「もし可能でしたら口コミをお願いできますか?」と伝える
- Google ビジネスプロフィールのリンクを LINE やメールで送る
- 手書きアンケートをスキャンしてホームページに掲載する
▶ 高評価レビューの効果
- 同業者との差別化になる
- 検索順位に間接的に好影響を与える(エンゲージメント評価)
- 「他の人も満足している」という社会的証明を得られる
▶ **口コミは“無料で得られる最大の信頼資産”**です。積極的に集めて活用しましょう。
継続的な更新が「生きているサイト」の証
Google は「更新されているサイト」「動きのあるサイト」を好みます。
定期的に以下のようなコンテンツを更新することで、SEO と信頼性を同時に強化できます。
- お知らせ(事務所移転・対応範囲変更など)
- 実績紹介(許認可の取得件数など)
- 法改正に関する情報提供(ブログやコラム)
▶ “1 ページも更新されていないサイト”より、“最新情報があるサイト”の方が信頼されやすいのは当然です。
まとめ:運用こそが「成果を出す鍵」
ホームページを制作したあとに、手を加えずに放置してしまっている事務所は少なくありません。
しかし、それではせっかくの集客ツールが“ただの名刺”になってしまいます。
SEO、Google マップ、口コミ、更新。
これらを地道に積み上げることで、**「見つかる・信頼される・依頼される」サイトへと成長させることができるのです。
あなたの事務所に合ったホームページを作ろう
ここまで、行政書士がホームページを制作・運用する上で必要な考え方・構成・具体的な実践方法について、10,000 文字を超えるボリュームで解説してきました。
最後に、これまでの内容を振り返りながら、**「あなたの事務所にとって最適なホームページとは何か?」**を一緒に考えてみましょう。
ホームページは「営業担当」であり「信用の証」
行政書士という仕事は、「資格がある」だけでは選ばれません。
依頼者が重視するのは、信頼できそうか・実績があるか・話しやすそうかといった「印象」と「安心感」です。
その最初の印象を決めるのがホームページであり、
24 時間 365 日働き続けるあなたの営業担当であり信用の証明書でもあります。
📌 チラシや名刺の代わりに URL を渡す時代
📌 事務所に来る前にホームページを見られる時代
📌 Google で「○○ 市 行政書士」と検索される時代
この現実を踏まえると、ホームページを持たない・あるいは作ったまま放置することが、どれほど機会損失につながっているかが分かるはずです。
自分に合った形でスタートすれば OK
「完璧なホームページを作らなきゃ」と気負う必要はありません。
大事なのは、**“自分の業務に合った形で無理なく始める”**ことです。
- 予算が限られていれば → STUDIO や Wix で自作+最低限の内容でスタート
- 本気で集客したい → 制作会社に依頼して設計+見た目の信頼性を高める
- 最初は簡易的でも → 後からページ追加・改善すれば OK
▶ 大事なのは「公開し、育てていくこと」。ホームページは“完成品”ではなく、“成長していくツール”です。
本記事で紹介した 10 のステップを再確認
- なぜホームページが必要なのか(信頼・集客・差別化)
- ホームページの役割(営業・信用のダブル機能)
- ターゲット・サービス・差別化の明確化
- 掲載すべきコンテンツの全体像
- 信頼感と使いやすさを両立したデザイン設計
- 自作 vs 外注の選び方と判断軸
- 費用の相場とコスパ重視の選び方
- 実際に成果が出ている事例から学ぶ戦略
- 公開後に必須の SEO・マップ・口コミ対応
- 継続的な運用と改善が成果のカギ
▶ これらを順に進めていけば、あなたの事務所にぴったりのホームページを無理なく構築できます。
最後に|ホームページは「未来の依頼者」との接点
現在あなたのホームページを訪れる人の多くは、**「いま困っていて、誰に相談しようか探している人」**です。
その人に「ここに相談してみよう」と思ってもらえるかどうか。
その分かれ道に立っているのが、あなたのホームページです。
これまでの人生で積み上げてきた経験や誠実さを、
“オンライン上でも伝えられる存在”が、よく設計されたホームページなのです。
あなたのホームページが、「安心して頼れる行政書士」として多くの人とつながるきっかけになることを願っています。
✅ 行政書士のホームページ制作なら、【株式会社 KUBOYA】にお気軽にご相談ください。
📘 続けて読みたい関連記事
👉 【保存版】行政書士のホームページ制作に強いおすすめ制作会社 10 選【全国対応】