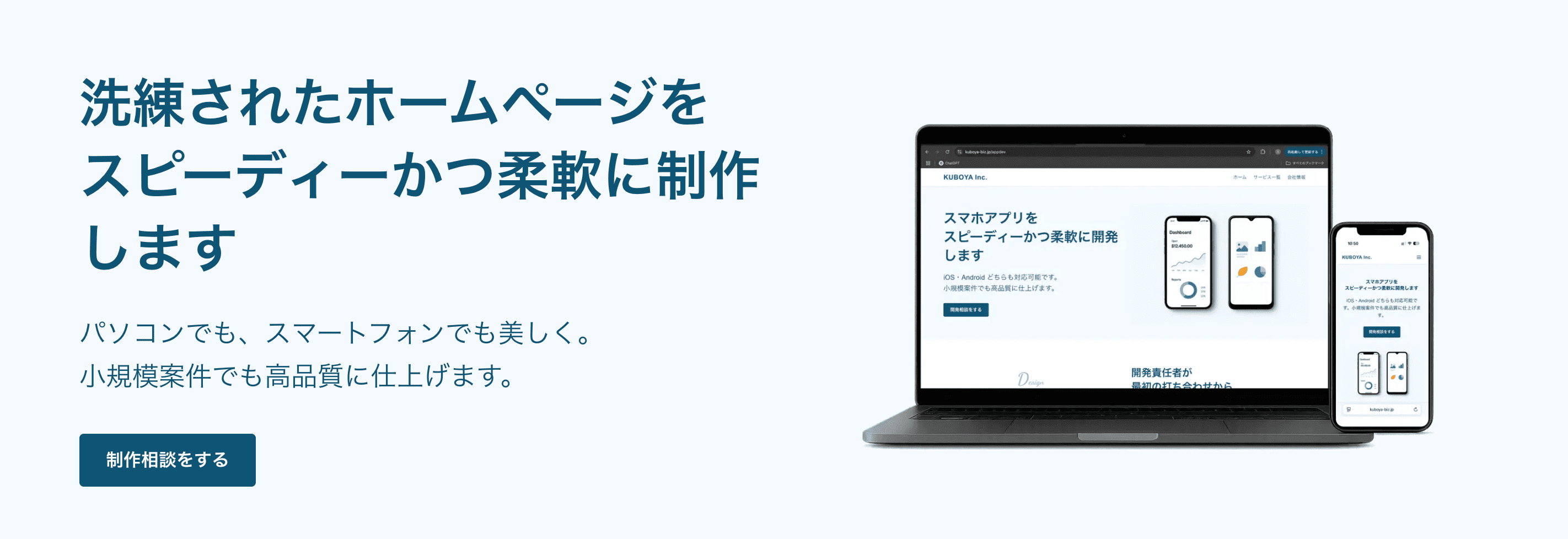中小企業診断士のホームページ制作|信頼されるサイト構成と費用相場
2025-05-28
監修:久保谷 太志
経済産業大臣認定 中小企業診断士 / Web制作ディレクター
目次

中小企業診断士がホームページを持つべき理由とは
「中小企業診断士として独立したけど、紹介だけでやっていけるだろうか…」
「ココナラやマッチングサイトに頼らず、安定的な依頼ルートを作りたい」
そんな悩みを抱えている方にとって、ホームページは“営業しない営業マン”としての役割を果たす重要な資産です。
ここでは、中小企業診断士がホームページを持つべき具体的な理由を 5 つの観点から解説します。
✅ 中小企業診断士のホームページ制作なら、【株式会社 KUBOYA】にお気軽にご相談ください。
1. 信頼感を可視化できる「名刺代わり」の役割
中小企業診断士は、企業経営の中核を担う“信頼ビジネス”。
クライアント企業の経営に関わる以上、「この人に任せても大丈夫か?」という第一印象の信頼性が非常に重要です。
ホームページを持つことで、
- 顔写真・経歴・資格・支援実績を明記できる
- 専門領域(例:補助金/事業再構築/事業承継など)を明確に伝えられる
- 士業らしい落ち着いたデザインで信頼感を演出できる
といった効果により、初対面の不安を軽減し、安心感ある相談導線を作ることができます。
2. 「中小企業診断士+地域名+業務名」で検索されている
Google などで実際に検索されているキーワード例を見てみると:
- 「中小企業診断士 補助金 支援 東京」
- 「事業再構築補助金 コンサル 大阪」
- 「経営改善計画 作成 兵庫 中小企業診断士」
など、“業務 × 地域”で探している中小企業が多く存在しています。
つまり、SEO 対策を施したホームページを持っていれば、自然検索からの相談・依頼を得ることができるのです。
ポータルサイト頼みではない、自前の集客チャネルを作ることが可能になります。
3. 売上を安定させる「問い合わせ窓口」を自社で持てる
ホームページを通じて安定的に問い合わせが入るようになると、以下のような事業の安定化メリットがあります:
- 継続顧客以外からも新規案件が入ってくる
- 受託案件に依存せず、自社サービス(顧問/研修/書籍など)へ展開可能
- 紹介元やマッチングサイトに手数料を払う必要がない
ホームページ=「自分でコントロールできる集客基盤」を持つことは、中長期の事業戦略にも大きく寄与します。
4. 補助金支援など「差別化」できる強みを発信できる
診断士の仕事は非常に幅広いため、ホームページがなければ「何が専門なのか」が伝わりません。
以下のような強み・実績・スタンスを可視化することで、他の診断士との差別化が可能です。
- 補助金支援実績(採択率・件数・対象業種など)
- 公的支援機関での実績(よろず支援拠点/商工会議所など)
- 小規模事業者支援への想い・姿勢
- 顧問契約型の支援・講演・セミナー登壇歴
→ これらは対面営業では伝えにくいが、Web ならじっくり伝えられる要素です。
5. 補助金申請・法人化・助成金対応にも役立つ
実はホームページは、ただの集客ツールではありません。
以下のような行政支援や法人取引にもプラスに働くのです。
- 【補助金対応】:「自社サービスの PR 手段」として申請要件に合致
- 【法人化・登記】:「企業ホームページ」として信頼度がアップ
- 【連携先拡大】:士業・金融機関・支援機関との接点が増える
「持っていて当たり前」の時代だからこそ、ホームページがない=怪しまれる・敬遠される要因にもなりかねません。
💡 コラム:実際の検索行動はこうなっている
中小企業経営者の Web 検索行動の一例:
① Google で「補助金 サポート 福岡」などで検索
② 上位 3 件のホームページをざっと比較
③ 顔写真・料金・対応内容・所在地が明記されている人に問い合わせる
つまり、**「ホームページがなければ最初の候補にすら入らない」**のが現実です。
✅ まとめ|中小企業診断士こそホームページを持つべき
| 理由 | 効果 |
|---|---|
| 信頼感の可視化 | 初対面でも安心して問い合わせてもらえる |
| SEO 集客 | 地域名 × 業務名で検索に引っかかる |
| 相談窓口の整備 | 紹介やポータルに依存しない営業が可能 |
| 差別化ポイント発信 | 専門領域や実績を明示できる |
| 行政・法人対応強化 | 信用・連携・補助金申請にも有利 |
ホームページは、名刺・営業資料・実績一覧・窓口・採用ツールのすべてを兼ね備えた「経営資産」です。
診断士という“信頼と実績がすべて”の職業にとって、ホームページは単なる装飾ではなく、武器になります。
信頼される中小企業診断士サイトの共通点とは
中小企業診断士のホームページは、単に「名刺代わり」ではなく、信頼感の構築と差別化の鍵を握るツールです。
では、実際に成果を上げている中小企業診断士のホームページには、どのような共通点があるのでしょうか?
以下では、成功している診断士サイトに見られる「信頼されるための要素」を具体的にご紹介します。
✅ 1. 顔が見える:写真とプロフィールがしっかり掲載されている
士業に限らず、顔が見える=安心感が高まるというのは Web マーケティングの鉄則です。
- プロによる自然な笑顔の写真
- 経歴・資格・支援実績の明示
- 「なぜ診断士になったのか?」といった想いやストーリー
→ これらがあると、「この人に相談してみたい」と感じてもらいやすくなります。
📌 顔出しができない場合でも、イラスト+経歴+理念の 3 点は最低限記載を。
✅ 2. 「誰に」「何を」提供するのかが明確
診断士の業務は幅広いため、専門性や対象者を明示することが重要です。
例:
- 「小規模事業者向けに補助金申請・経営計画作成を支援します」
- 「飲食・観光業に特化した事業再構築支援」
- 「創業支援と資金調達に強い中小企業診断士です」
→ このように、「誰に」「どんな支援をしているか」がファーストビューでわかる構成にすることで、問い合わせの質も向上します。
✅ 3. 業務内容が具体的かつ実績ベースで書かれている
単に「経営支援します」「課題解決をサポートします」と書くだけでは、他サイトとの差別化ができません。
実績ベースで記載する例:
| ダメな例 | 良い例 |
|---|---|
| 経営支援に対応します | 月商 300 万円 →600 万円に改善した飲食店支援(実例) |
| 補助金申請に対応可能です | 採択率 92%/累計 250 件以上の補助金支援実績 |
→ 数値・件数・ストーリーなどを交えて記載すると、説得力が大幅にアップします。
✅ 4. 料金が明記されている(安心感)
価格が明記されていないホームページは、**「問い合わせづらい」「なんとなく不安」**という印象を与えてしまいます。
- 初回相談:無料 or ◯ 円
- 補助金申請支援:◯ 円~
- 経営改善計画:基本料金 ◯ 円+成果報酬 ◯%
など、最低限の目安があるだけでも問い合わせ率は向上します。
📌 あえて詳細な金額を載せない場合でも、「料金体系の考え方」は必ず記載しましょう。
✅ 5. 問い合わせがしやすい導線設計
いくらサイトの内容が良くても、**「問い合わせボタンが見つからない」「面倒そう」**では機会損失につながります。
信頼されるサイトに共通する UI/UX 設計:
- 常に画面右上 or フッターに「お問い合わせ」ボタン
- LINE・メール・電話など複数手段に対応
- フォームは 3 ~ 5 項目程度のシンプル設計
- 対応時間や返信目安の明記
→ 問い合わせのハードルを下げる=信頼と親切の証でもあります。
✅ 6. 継続的に情報発信している(更新頻度)
更新されていないサイトは、「廃業しているのでは?」という不安を与えることも。
- 補助金や制度改正のコラム
- 実績やお客様の声の紹介
- セミナー登壇や活動報告
→ これらを月 1〜2 回更新するだけでも、信頼性と専門性が伝わります。
✅ 7. 専門キーワードに対応した SEO 設計
検索からの集客を狙う場合、見出し・URL・ページタイトルに「業務名+地域名」を含めることが重要です。
- 補助金申請コンサル 大阪
- 経営改善計画 診断士 東京
- 創業計画サポート 愛知
→ 信頼されるサイトほど、検索意図に合ったページ構成が整っています。
💡 ワンポイント:サイト訪問者は「比較」している
ユーザーは 1 サイトだけで決めるのではなく、複数の診断士サイトを比較した上で問い合わせをします。
そのため、以下の観点が“他と比べてどうか”が見られます:
| 見られる要素 | 比較されるポイント |
|---|---|
| 顔・プロフィール | 親しみやすさ・信頼性 |
| 実績・事例 | 数量と具体性 |
| 専門性 | 自社に合うかどうか |
| 対応範囲 | 地域・業種・テーマ |
| 料金 | 目安・明朗さ |
✅ まとめ|信頼される診断士サイトは“中身”で勝負している
| 共通点 | 意味・効果 |
|---|---|
| 顔が見えるプロフィール | 安心・親しみ・共感を生む |
| 専門性の明示 | 他との差別化につながる |
| 実績の具体化 | 信頼と説得力を高める |
| 料金の明記 | 問い合わせハードルを下げる |
| UI/UX の工夫 | 問い合わせ率アップ |
| 定期的な更新 | 活動の継続性・真剣さを伝える |
| SEO 対応 | 潜在顧客の流入を獲得 |
診断士の仕事は「人」が選ばれる世界。
その「人となり」を、第三者に伝えてくれるのがホームページです。
見た目の美しさだけではなく、中身の充実こそが信頼を勝ち取るカギになります。
中小企業診断士ホームページに必須の構成掲
信頼され、選ばれる中小企業診断士サイトには、一定の構成パターンがあります。
ただ「かっこいいデザイン」や「最新トレンド」を追うのではなく、見やすく、わかりやすく、信頼される情報設計が何よりも重要です。
ここでは、診断士ホームページに必ず盛り込むべきページ構成と内容要素を詳しく解説します。
✅ 1. トップページ(ファーストビュー+概要)
最も重要なページであり、訪問者が 3 秒以内に「この人に相談して良さそう」と思えるかが決まります。
含めるべき内容:
- キャッチコピー(例:「補助金申請に強い中小企業診断士」)
- 対応業務の一覧(アイコンや短文で)
- 顔写真と簡単なあいさつ文
- 問い合わせボタン/LINE ボタン
ファーストビューに「誰に・何を提供しているか」が伝わると、離脱率が大きく下がります。
✅ 2. ごあいさつ・プロフィールページ
中小企業診断士は「人で選ばれる」仕事。
資格・経歴だけでなく、信念や人柄が伝わる内容が好まれます。
掲載すべき情報:
- 診断士になったきっかけ・想い
- 経歴やこれまでの職歴
- 保有資格(例:中小企業診断士、MBA、IT パスポート等)
- 家族構成や出身地(あれば親近感 UP)
他士業との差別化にもつながるページです。写真の質にもこだわりましょう。
✅ 3. 業務内容ページ(サービス案内)
「この業務をお願いできるかどうか」が明確に伝わらなければ、問い合わせは発生しません。
おすすめの構成:
- 各業務を個別ページ化(補助金、経営改善、創業支援など)
- サービスの流れ(ステップ形式)
- 成果事例の紹介(簡単な実績)
- 対応可能な地域・業種の明示
業務ページには**検索キーワード(例:補助金申請 大阪 中小企業診断士)**を入れると SEO にも効果的です。
✅ 4. 料金ページ(報酬・費用の目安)
料金が載っていないサイトは「不安」「連絡しづらい」という印象を持たれやすいです。
すべての費用を細かく載せる必要はありませんが、目安は明記すべきです。
掲載例:
| サービス | 費用目安(税込) |
|---|---|
| 補助金申請支援 | 着手金 3 万円+成功報酬 10% |
| 創業計画書作成 | 5 万円〜 |
| 顧問契約(月額) | 3 万円〜 |
「無料相談あり」「初回はオンライン対応可」などの情報も信頼につながります。
✅ 5. お問い合わせページ
「問い合わせしやすさ」は、サイトの成果を大きく左右する要素です。
理想の構成:
- シンプルなフォーム(名前/連絡先/相談内容)
- LINE・メール・電話いずれにも対応
- 対応可能時間・定休日の明記
- プライバシーポリシー(必須)
常時表示の「お問い合わせ」ボタンを設置しておくと、離脱を防げます。
✅ 6. 実績・お客様の声(できれば掲載)
他の診断士との差別化に最も効果的なのが「第三者からの評価」です。
支援事例やお客様の声があるだけで信頼性が段違いになります。
掲載方法:
- 匿名でも OK(業種・規模・成果を記載)
- 支援前と支援後の変化(例:売上アップ/補助金採択など)
- クライアントの声(短文でも十分)
許可が取れれば、顔写真や会社名ありの声がより効果的です。
✅ 7. ブログ・お知らせ(情報発信)
サイトに動きがあることは「現役で活動している」証明になります。
また、SEO にも好影響です。
発信内容の例:
- 補助金や制度改正の速報
- 経営ノウハウや事例紹介
- セミナー・メディア出演情報
- 年末年始などの営業日案内
月 1 本でも更新されていれば、検索評価や訪問者の印象が大きく変わります。
✅ 8. よくある質問(FAQ)
FAQ を設けることで、問い合わせ前の不安を和らげ、対応工数も削減できます。
例:
- 初回相談は無料ですか?
- 対面以外でも対応してもらえますか?
- 契約前に見積もりは出せますか?
- 土日や夜間の対応は可能ですか?
✅ 9. アクセス情報・対応地域
「近くの診断士に相談したい」というニーズは根強くあります。
掲載内容:
- 事務所の所在地・Google マップの埋め込み
- 対応可能なエリア(例:東京 23 区+千葉西部など)
- 出張相談やオンライン対応の有無
完全オンライン対応の場合も、拠点の住所は記載しておきましょう。
✅ 10. SNS リンク(任意)
SNS を運用している場合は、ホームページと連携しておくことで信頼感・親近感が向上します。
- Facebook(セミナー報告など)
- X(旧 Twitter):情報発信や人柄表現に ◎
- LINE 公式アカウント:相談窓口として有効
🧠 まとめ:必要な構成を漏れなく押さえることが信頼につながる
| ページ名 | 目的・役割 |
|---|---|
| トップページ | 印象・全体の要約・導線の確保 |
| プロフィール | 人柄・信頼感の訴求 |
| 業務内容 | 具体的な対応領域と専門性の提示 |
| 料金案内 | 安心感・予算感の明確化 |
| 問い合わせ | スムーズな導線設計 |
| 実績・声 | 社会的証明・信頼の後押し |
| ブログ・更新 | 情報発信・SEO・活発な印象 |
| FAQ | 不安解消・問い合わせの後押し |
| アクセス情報 | 地域性・対応エリアの明示 |
| SNS リンク | 補完的な信頼形成・継続的接点 |
「なんとなく作る」では成果は出ません。
中小企業診断士として成果を出すサイトを目指すなら、構成は“戦略”として設計するべき項目です。
次のステップでは、**これらをどう見せるか=「デザインと流れ」**についても考えていきましょう。
✅ 中小企業診断士のホームページ制作なら、【株式会社 KUBOYA】にお気軽にご相談ください。
集客できるサイトとそうでないサイトの違い
せっかくホームページを作ったのに、「問い合わせが一件も来ない」「結局、名刺に URL を載せているだけ」…
そんな状況に陥る診断士も少なくありません。
一方で、ホームページ経由で毎月安定的に問い合わせが入る診断士もいます。
この違いは、一体どこにあるのでしょうか?
ここでは、集客できる中小企業診断士のホームページに共通するポイントと、集客に失敗してしまうサイトの問題点を対比しながら解説します。
✅ 比較表|集客できるサイト vs 集客できないサイト
| 項目 | 集客できるサイトの特徴 | 集客できないサイトの特徴 |
|---|---|---|
| 専門性の打ち出し方 | 特定業務(例:補助金/創業支援)に絞って発信している | 「何でもできます」と広く浅い表現に終始している |
| SEO 対策 | タイトル・URL・見出しにキーワードを含めている | タイトルが抽象的で検索に引っかからない |
| 実績の提示 | 数値・事例・顧客の声が具体的に掲載されている | 実績に触れておらず、信頼感が乏しい |
| CTA(行動喚起)の配置 | 問い合わせボタンが常に目に入り、迷わず連絡できる | お問い合わせフォームが目立たず、導線が不明瞭 |
| 表現の親しみやすさ | 顔写真+プロフィール+ストーリーがあり、人間味が伝わる | 無機質な説明文と資格だけで終わっている |
| 更新頻度・情報の新しさ | ブログやお知らせが月 1〜2 本以上更新されている | 最終更新が 1 年以上前、放置されている印象を与える |
| ページ速度・スマホ対応 | スマホ表示でもスムーズ、読み込みが速い | 表示が崩れていたり、文字が小さく読みにくい |
✅ 1. 「何を専門にしているか」が一目でわかるかどうか
中小企業診断士の業務は幅広いため、訪問者は“自分のニーズに対応しているか”を真っ先に確認します。
【良い例】「補助金支援に特化|建設業や製造業を中心に年間 50 件以上支援」
【悪い例】「経営のご相談はお任せください」
→ どんな業種・どんな支援・どの地域に強いのかを具体的に伝えることが重要です。
✅ 2. 「実績・証拠」があるかどうか
ネットで見つけた診断士に仕事を頼むのは、多くの経営者にとってリスクのある選択です。
その不安を取り除くには、第三者的な証拠(=実績や声)が欠かせません。
例:
- 採択率・支援件数・支援規模の掲載
- 実績の写真や図解
- クライアントの声・レビュー・アンケート結果
数字とストーリーで語れる診断士サイトは、集客力が段違いです。
✅ 3. 「行動喚起(CTA)」が明確に設計されているか
集客できるサイトは、訪問者に**次の行動を具体的に促す導線(CTA)**がしっかり設計されています。
- 各ページに「無料相談はこちら」ボタン
- LINE 公式への誘導
- フォームまで 1 クリックで移動できる
逆に、CTA がなかったり曖昧だったりすると、「とりあえず見ただけ」で離脱されてしまいます。
✅ 4. 「人となり」が伝わるかどうか
診断士は“信頼と相性で選ばれる職業”。プロフィール写真・自己紹介文・支援への想いがしっかり書かれているだけで、選ばれる確率が上がります。
「資格だけではなく、人柄で選んでもらう時代」です。
✅ 5. 検索流入の設計(SEO)をしているか
以下を押さえていないホームページは、検索で発見されず埋もれてしまいます。
- タイトルタグに「業務名+地域名+診断士」を含める
- 各ページにキーワード(補助金/事業再構築/創業など)を適切に配置
- 画像にも alt テキストを入れる
→ 記事や業務ページの構造とキーワード設計を意識して作ることで、Google からの流入が増えます。
✅ 6. 定期的に更新されているかどうか
更新されていないサイト=「活動していない人」と誤解される可能性があります。
- ブログ(月 1 でも OK)
- お知らせ(「夏季休業のお知らせ」なども効果的)
- 実績追加や声の更新
→ 少しでも更新履歴があると「この人は現在進行形で活動している」と感じてもらえます。
✅ 7. 表示スピード・スマホ対応
モバイル端末での閲覧が主流となった今、表示速度やスマホ最適化は信頼性の一部です。
- 表示が遅い=「ちゃんとしてなさそう」
- スマホで操作しづらい=「古い印象」
→ Web デザインや CMS(WordPress 等)の最適化も、集客できるサイトには必須です。
✅ まとめ|「集客できない理由」は設計と中身にある
| チェック項目 | あてはまらない場合は改善ポイント |
|---|---|
| 専門性が伝わっているか? | 「何でもできます」は NG。絞り込む |
| 実績・声があるか? | 数値・事例・第三者の評価で信頼を得る |
| 問い合わせ導線は明確か? | CTA ボタン・導線を全ページに配置 |
| 人柄が見えるか? | プロフィール・写真・ストーリーを加える |
| SEO を意識しているか? | 業務 × 地域 × 診断士を意識して設計する |
| 定期的に更新しているか? | ブログやお知らせを月 1 本でも発信する |
| モバイル対応しているか? | 今の Web ではスマホ最適化は必須 |
ホームページは作って終わりではありません。
集客できる設計をし、信頼される中身を整え、定期的に育てていくことで、Web からの安定的な案件獲得が可能になります。
ホームページ制作の流れ
中小企業診断士として信頼感のあるホームページを作るには、やみくもに制作を始めるのではなく、目的と設計に基づいた段階的な進行が重要です。
ここでは、診断士が実際にホームページを制作する際の一般的な流れを、7 つのステップに分けて詳しく解説します。
✅ STEP1:目的とターゲットの明確化
まず最初に行うべきは、「何のためにホームページを作るのか」を明確にすることです。
- 新規顧客の獲得(集客)
- 信頼性の確保(名刺代わり)
- 補助金や創業支援の専門性を訴求
- 地域名での SEO 流入を狙う
ターゲット(例:創業間もない経営者、建設業の経営者など)も明確にしておくことで、構成やデザインがブレずに進行します。
✅ STEP2:掲載内容・構成の整理
次に行うのが、ホームページにどんな情報を掲載するかの整理です。
- トップページ(強み・サービス概要)
- プロフィール(資格・経歴・理念)
- サービス紹介(業務別に整理)
- 実績・お客様の声
- よくある質問
- ブログやお知らせ
- お問い合わせフォーム
→ この段階でワイヤーフレーム(画面構成図)を作成することで、制作会社との認識ずれを防げます。
✅ STEP3:制作会社の選定・打ち合わせ
信頼できる制作会社を選定し、初回打ち合わせを行います。
打ち合わせでは以下の内容を確認しましょう:
- サイトの目的・ターゲット
- 希望するデザインや雰囲気(参考サイトなど)
- 更新のしやすさ(WordPress 等の利用可否)
- 納期・費用の見積もり
- SEO 対策やスマホ対応の有無
✅ 士業専門や診断士対応実績のある会社を選ぶとスムーズです。
✅ STEP4:デザイン制作・構築
デザイナーがトップページ・下層ページのデザイン案を作成し、確認を経てサイト構築に入ります。
- デザイン案は修正可能か確認
- 色・フォント・写真素材の確認
- スマホ対応の UI もチェック
この段階でテストサイトを見ながら進行するのが一般的です。
✅ STEP5:原稿・写真の準備と反映
診断士本人が準備する必要のある主な素材は以下の通り:
- プロフィール文・顔写真
- サービス紹介文(できるだけ具体的に)
- 実績・お客様の声
- 事務所写真・イメージ写真
**原稿準備が遅れると全体のスケジュールも遅延します。**制作会社がライティングをサポートしてくれることもあるので、相談しましょう。
✅ STEP6:公開前チェック・最終確認
すべてのページが完成したら、事前にテスト環境で動作や内容を確認します。
- 表記ミスやリンク切れがないか
- 問い合わせフォームが動作しているか
- スマホ表示・読み込み速度に問題はないか
- Google にインデックスされる設定か(noindex で公開されていないか)
✅ 必要であれば、Google Analytics や Search Console の設定も依頼しましょう。
✅ STEP7:本番公開・運用スタート
すべての確認が済んだら、いよいよ本番ドメインでの公開です。
- 事務所の名刺やパンフレットに URL を記載
- SNS やポータルサイトからのリンクも整備
- 月 1 回程度のブログ更新で SEO 効果をキープ
ホームページは“育てる”もの。
公開後も改善・更新を続けることで、問い合わせや信頼性は着実に積み上がっていきます。
✅ 補足|制作期間の目安と注意点
| 内容 | 期間の目安 |
|---|---|
| 打ち合わせ〜構成確定 | 約 1〜2 週間 |
| デザイン〜初稿提出 | 約 2 週間 |
| 修正・構築・最終確認 | 約 1〜2 週間 |
| 合計 | 約 1 ヶ月前後 |
※原稿提出や確認がスムーズに進めば 1 ヶ月以内で公開可能。
ただし診断士側の対応が遅れると 2〜3 ヶ月かかるケースもあります。
ホームページ制作の流れを理解しておけば、「失敗しない制作依頼」が可能になります。
外注だからと任せきりにせず、要所で診断士本人が関与することで、「伝わるサイト」に仕上がります。
自作と外注はどっちがいいか
ホームページ制作には「自分で作る」方法と「外注する」方法があります。
中小企業診断士にとって、どちらが本当に良いのでしょうか?
ここでは、自作と外注のそれぞれのメリット・デメリットを比較しながら、どんな人にどちらが向いているかを解説します。
✅ まず比較!自作 vs 外注の特徴一覧
| 項目 | 自作の特徴 | 外注の特徴 |
|---|---|---|
| 初期コスト | 低い(0 円〜数千円) | 中〜高(5 万円〜30 万円程度が一般的) |
| 制作スピード | 早ければ数日で可能 | 通常 1〜2 ヶ月かかる |
| デザイン品質 | テンプレートレベル | プロの手によるオリジナルデザイン |
| SEO 対策 | 知識があれば対応可能、なければ弱い | 初期設計からキーワード選定、構造化まで配慮される |
| スマホ対応・高速化 | テーマによる制限あり | スマホ表示・表示速度の最適化も含まれる |
| ブログ機能 | 無料ブログや WordPress で対応可能 | WordPress 構築やカスタム CMS に対応 |
| 保守・更新 | 自分で随時可能 | 更新依頼 orCMS 導入による自己更新 |
| 時間コスト | 高い(学習+作業) | 低い(コンテンツ提供のみで OK) |
✅ 自作がおすすめな中小企業診断士
以下に当てはまる方は、まずは自作からスタートしてみるのも良いでしょう。
- 副業診断士として活動中で、費用をかけたくない
- ブログや Web 制作の基礎知識がある
- テンプレートでも構わないから早く公開したい
- 趣味的に Web を触るのが好き
💡 無料サービス(ペライチ、Wix、STUDIO など)も選択肢に入ります。
ただし、「なんとなく作って満足」になりがちで、集客効果や信頼性に欠けるケースが多いため、公開後は定期的な改善が必要です。
✅ 外注がおすすめな中小企業診断士
以下の条件に当てはまるなら、迷わずプロに外注する方が結果的にコスパが良くなります。
- 本業が忙しく、自作の時間がない
- 開業後すぐに問い合わせがほしい
- ブランディングや信頼性を高めたい
- SEO やスマホ対応なども最適化したい
- 継続的に運用・更新していきたい
💡 プロの制作会社は、「集客できる構成」「CV(問い合わせ)導線設計」に長けており、結果に繋がるホームページが期待できます。
✅ 外注といっても方法は複数ある
| 外注方法 | 特徴 | 費用感 |
|---|---|---|
| 制作会社 | 士業に強い会社なら構成・文章まで丸ごと依頼可能 | 10 万円〜30 万円 |
| フリーランス | 価格は安め、個人対応なので柔軟性は高いが相性に注意 | 5 万円〜15 万円 |
| クラウドサービス | ペライチ Pro などで「半外注」的なサポートが受けられる | 月額 3,000 円〜 |
✅ 最後に|目的と予算に応じた選択を
| 目的 | おすすめ手段 |
|---|---|
| まずは名刺代わりに 1 ページ | 無料サービスで自作 |
| 最低限の SEO も欲しい | WordPress で自作 |
| 集客と信頼性を両立したい | 制作会社に外注 |
| ブログや実績を継続発信 | WordPress +外注 |
ホームページは「作ること」が目的ではなく、“成果を出すこと”がゴールです。
そのためには、時間やお金をどう使うか、診断士自身のフェーズに応じて最適な手段を選びましょう。
制作費用の相場と内訳|初期費用・月額の目安は?
中小企業診断士としてホームページを立ち上げたいけれど、
「一体いくらかかるのか?」
「月額は必要?」
と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
ここでは、ホームページ制作にかかる費用の相場とその内訳を解説しつつ、コストを抑えるポイントについても紹介します。
✅ 制作費用の全体像|まずは目安を知ろう
| 項目 | 相場の目安 |
|---|---|
| 初期費用 | 5 万〜30 万円程度 |
| 月額費用 | 0〜1 万円程度(保守含む) |
| ドメイン取得 | 年間 1,000〜3,000 円 |
| サーバー費用 | 年間 5,000〜15,000 円 |
| オプション例 | 写真撮影・ロゴ作成など |
⚠ 費用は制作方法・依頼先・サイト規模によって大きく変動します。
✅ 初期費用の内訳とは?
「初期費用」と一口に言っても、その内訳を知ることで見積もり内容の比較・判断がしやすくなります。
| 内容 | 解説 |
|---|---|
| 企画・構成設計 | ターゲット設定、導線設計、ページ構成など |
| デザイン制作 | トップページ・下層ページのビジュアルデザイン |
| コーディング | HTML/CSS/JavaScript などによるページの実装 |
| スマホ対応 | レスポンシブ対応など(最近は標準で含まれることが多い) |
| フォーム設置 | お問い合わせや資料請求フォームなど |
| CMS 構築(WordPress) | ブログ投稿や自分で更新可能なシステムの導入 |
| SEO 対策(初期) | メタ情報の設定、構造化データ、表示速度最適化など |
✅ 月額費用はなぜ発生するのか?
制作会社によっては、公開後に月額費用が発生するケースもあります。
その内訳は以下のようなものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サーバー管理費 | サイトの安定稼働のためのホスティング費用 |
| ドメイン維持費 | 独自ドメインの年間更新費用(初期費用に含む場合もあり) |
| 保守・運用サポート | 不具合対応、セキュリティ対策、CMS アップデート対応など |
| 軽微な修正対応 | テキストや画像の差し替えなど(回数制限あり) |
💡 月額が発生するかどうかは、事前にしっかり確認しましょう。
✅ よくある制作プラン例
| プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ライトプラン | 5 万円前後 | 0〜3,000 円 | テンプレート使用・固定ページのみ |
| スタンダード | 10〜20 万円 | 5,000〜8,000 円 | オリジナルデザイン・ブログ機能付き |
| プレミアム | 25〜30 万円以上 | 1 万円以上 | 戦略設計・SEO 強化・サポート込み |
✅ 費用を抑えるための 3 つのポイント
① 写真・原稿を自分で用意する
プロに任せると追加費用がかかることが多いため、自前で準備することで大幅に節約可能です。
② WordPress などの CMS を導入
一度作れば更新が自分でできるため、将来的な運用コストを下げられます。
③ 無料ツールや補助金の活用
補助金(小規模事業者持続化補助金など)を活用することで、実質自己負担を半分以下に抑えることも可能です。
✅ 安かろう悪かろうに注意
「初期費用 0 円」「月額 980 円〜」といった低価格サービスもありますが、以下のような制限があることも:
- 自由にデザインできない
- サポートが手薄
- 解約後にデータが手元に残らない
費用だけで判断せず、“目的に合った価値”があるかを重視しましょう。
✅ 最後に|見積もりは必ず複数社で比較を
制作会社によって含まれる項目やサポート体制が大きく異なります。
診断士として信頼性を高めたいなら、最低でも 2〜3 社の見積もりを取得して比較検討するのがおすすめです。
診断士としての成果につながる制作会社の選び方
ホームページ制作を外注する場合、どの制作会社を選ぶかで結果が大きく変わります。
価格や見た目の良さだけで選ぶと、「問い合わせが来ない」「更新できない」など後悔することも。
ここでは、中小企業診断士にとって本当に成果につながる制作会社を選ぶための8 つのチェックポイントを紹介します。
✅ 1. 士業サイトの実績があるか?
中小企業診断士のホームページには、他業種とは違った専門性・信頼性・堅実な印象が求められます。
- 行政書士・社労士・司法書士など、士業の実績がある制作会社なら構成やトーンも適切。
- 実績ページに「士業の事例」があるかをチェック。
📌 実例が見られない場合は、問い合わせ時にポートフォリオを求めましょう。
✅ 2. 専門知識がなくても任せられるか?
診断士業務に集中したいあなたにとって、「構成・文案まで任せられるか」は非常に重要です。
- ヒアリングをもとに構成案を出してくれるか
- キャッチコピーやサービス紹介文まで提案してくれるか
✍️ 「診断士向けにこういう打ち出しが効果的です」といった提案がある会社は安心です。
✅ 3. SEO の基本対策が含まれているか?
制作会社によっては、見た目だけ整えて SEO 対策は別料金というケースもあります。
最低限チェックすべきポイント:
- タイトル・メタ情報の設定
- モバイル対応(レスポンシブ)
- 表示速度最適化
- パンくず・内部リンク構造
- Google 登録サポート
💡「検索で上位表示させたい」という目的があるなら、SEO が得意な会社を選びましょう。
✅ 4. WordPress などの CMS に対応しているか?
ブログ更新やお知らせ配信を続けたい場合、CMS(更新システム)対応かどうかは必須チェック項目です。
- WordPress など、自分で更新できる設計か?
- 編集画面がわかりやすいか?
- サポートや操作マニュアルはあるか?
🧠 診断士は知見発信が命。自分で記事を投稿できる設計が望ましいです。
✅ 5. 運用サポートが充実しているか?
ホームページは作って終わりではなく、育てていくものです。
- 月額の保守費用の内容が明確か?
- 修正依頼やトラブル対応のスピードは?
- 更新の依頼方法(メール/チャットなど)は使いやすいか?
🔧 「軽微な修正は無料で月 2 回まで」など、具体的なサポート範囲が提示されていると安心です。
✅ 6. 担当者の対応は丁寧か?
価格や技術だけでなく、担当者との相性も重要です。
- ヒアリングに時間をかけてくれるか?
- 提案内容に納得感があるか?
- 無理な営業をしないか?
💬「この人になら任せられる」と感じる対応力も、成果を生む鍵となります。
✅ 7. 制作後の所有権・契約内容は明確か?
意外と見落とされがちですが、制作物の著作権・契約条件は必ず確認を。
- 解約後にドメインやデザインは引き継げるか?
- 月額契約の縛り期間はあるか?
- サイトのバックアップは提供されるか?
📑 契約書や利用規約は必ず確認し、曖昧な点は事前に質問しておきましょう。
✅ 8. 他社と比較したときに納得感があるか?
最後に、2〜3 社に相見積もりをとって比較することをおすすめします。
- 同じ要件でも費用が倍以上違うことも
- デザイン提案の質、説明の丁寧さも比較材料に
- 比較すると「相場感」が身につく
💡 価格だけでなく「成果につながるか」で判断する視点を持ちましょう。
✅ まとめ|診断士が選ぶべきは「成果に責任を持つ制作会社」
| NG な選び方 | OK な選び方 |
|---|---|
| 安さだけで選ぶ | 費用と成果のバランスを見る |
| 見た目重視だけ | 信頼・導線・SEO を考慮した設計かを見る |
| 担当者任せにする | 質問・相談を重ねながら、納得して進める |
中小企業診断士の価値をしっかり伝え、信頼される第一印象を作るには、良いパートナー選びが欠かせません。
迷ったら、まずは実績のある制作会社に無料相談してみるのも第一歩です。
よくある質問
Q1. ホームページを持つメリットはありますか?
あります。
特に中小企業診断士の場合、信頼性・実績・専門性を視覚的に伝えるツールとして非常に効果的です。
名刺だけでは伝わらない「自分の強み」や「サポート内容」を明確にできます。
Q2. どのタイミングで制作すべきですか?
独立開業前〜直後がベストです。
開業と同時にホームページが公開されていれば、名刺や SNS とも連携しやすく、初期の信頼獲得や SEO の蓄積も早まります。
Q3. スマホ対応は必須ですか?
必須です。
現在はアクセスの 7 割以上がスマホから。スマホで見やすく設計されていないと、離脱率や信頼性に大きな影響があります。
Q4. 制作にはどれくらいの期間がかかりますか?
一般的には3〜6 週間程度です。
構成の確定・原稿の準備・画像の選定などがスムーズに進めば、もっと短期間で公開可能な場合もあります。
Q5. 自分で更新できますか?
更新できる構成も選べます。
WordPress などの CMS を導入すれば、診断事例やお知らせ、ブログ記事などを自分で簡単に更新できます。
Q6. 制作会社に任せきりで大丈夫ですか?
基本的にはヒアリングベースで進められますが、自分の想いや専門分野をしっかり伝えることが重要です。
良い制作会社はその情報を整理して魅力的に表現してくれます。
Q7. 費用の相場はどのくらいですか?
10 万〜30 万円が一般的なスタートラインですが、ページ数や機能追加により30〜50 万円以上になるケースもあります。
補助金を活用することで、実質負担を軽減できます。
Q8. 補助金や助成金のサポートはありますか?
対応している制作会社も多くあります。
小規模事業者持続化補助金などの申請サポートを行っている会社を選べば、手続きもスムーズです。
Q9. ホームページを作っただけで集客できますか?
いいえ、作っただけでは不十分です。
SEO 対策・ブログ更新・SNS との連携など、運用も重要です。制作後のサポート体制も確認しておきましょう。
Q10. 制作会社はどうやって選べば良いですか?
- 士業(特に診断士)実績があるか
- SEO や運用に強いか
- 担当者の対応が丁寧か
- 契約内容・費用が明確か
を基準に、複数社を比較して選ぶのが理想です。
✅ 中小企業診断士のホームページ制作なら、【株式会社 KUBOYA】にお気軽にご相談ください。