デイサービスのホームページ制作ガイド|信頼を得る構成と費用相場
2025-06-07
監修:久保谷 太志
経済産業大臣認定 中小企業診断士 / Web制作ディレクター
目次
- はじめに|なぜ今、デイサービスにホームページが必要なのか?
- デイサービス業界の現状とホームページの役割
- デイサービスのホームページに必要な 7 つの基本情報
- 信頼感を高めるホームページの構成とデザインのポイント
- 競合サイトの事例比較|選ばれているデイサービスの共通点
- ホームページ制作の流れ|準備から公開・運用までの全体像
- デイサービスのホームページ制作にかかる費用相場
- サブスク型(定額制)ホームページ制作の選択肢とメリット
- 集客・信頼に効くオプション機能の活用例
- よくある質問(FAQ)
- 制作会社の選び方と依頼時のチェックポイント
- まとめ|信頼されるデイサービスを目指すなら、ホームページから整えよう
- ホームページ制作のご相談はお気軽にどうぞ
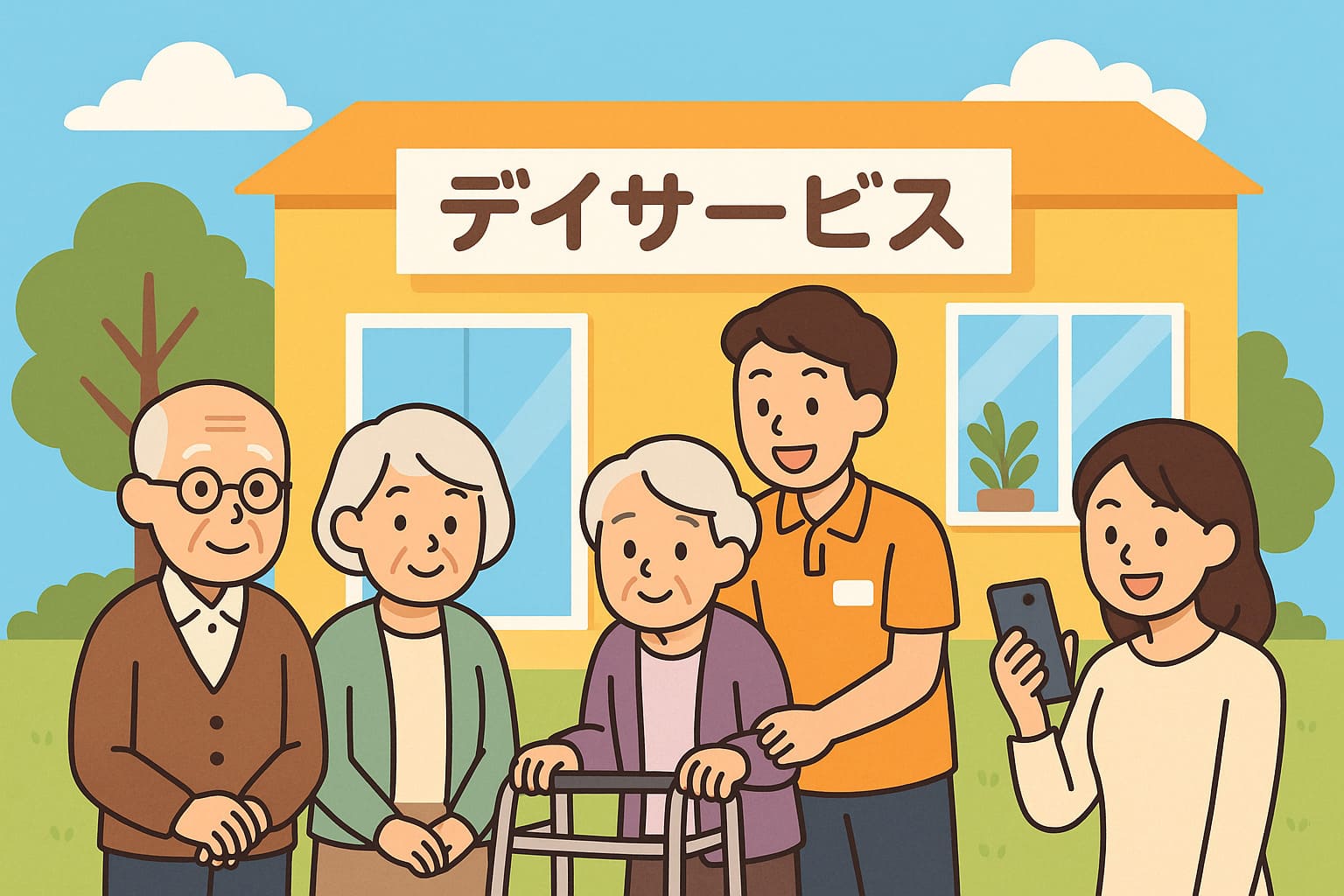
はじめに|なぜ今、デイサービスにホームページが必要なのか?
少子高齢化が急速に進む日本において、地域の高齢者を支えるデイサービスの役割は年々重要性を増しています。利用者本人だけでなく、その家族やケアマネジャーが「安心して任せられる施設かどうか」を判断する際に、ホームページの有無や内容が大きな判断材料となっているのが現実です。
従来であれば、ケアマネジャーからの紹介やパンフレットを通じた情報提供が主な集客手段でした。しかし今では、インターネット検索を通じて情報収集を行う家族が増えています。特に、遠方に住んでいるご家族が施設を検討する際には、信頼できる情報源としてのホームページの整備が不可欠です。
また、デイサービスは医療・介護に関する専門的なサービスを提供するため、他業種と比較しても信頼性・安全性・清潔感といった印象が重視される傾向にあります。ホームページがあることで、サービス内容や施設環境、スタッフの顔が「見える化」され、安心感のある情報発信が可能になります。
さらに、介護業界では人材不足も深刻な課題のひとつです。採用活動においても、応募者が最初にチェックするのがホームページであるケースが多く、しっかりと作り込まれたサイトは信頼性のアピールだけでなく、採用効率の向上にもつながります。
つまり今、デイサービスにおけるホームページは単なる情報掲載ツールではなく、「選ばれるための武器」であり、「信頼を得るための窓口」なのです。競合施設との差別化を図り、利用者や家族、スタッフからも選ばれる施設になるためには、高品質なホームページ制作が不可欠な時代と言えるでしょう。
デイサービス業界の現状とホームページの役割
高齢化と利用者の選択眼の変化
日本はかつてないスピードで高齢化が進んでおり、75 歳以上の人口が総人口の約 15%を超える時代に突入しています。こうした中で、デイサービスの需要は右肩上がりですが、それと同時に利用者やその家族の「選ぶ目」も年々厳しくなっています。
かつては「近いから」「空いているから」といった理由で施設を選ぶことが一般的でしたが、現在ではサービスの質や雰囲気、スタッフの対応力、リハビリメニューの充実度などを重視する傾向が強まっています。インターネットや SNS、口コミサイトを駆使して情報収集を行い、複数の施設を比較検討する時代に変わってきているのです。
このような環境では、「どのようなサービスを提供しているのか」「どんな雰囲気なのか」をわかりやすく伝えるツールとして、ホームページの役割が非常に重要になります。
家族・ケアマネジャーに選ばれるために
実際にデイサービスを利用するかどうかを決めるのは、本人ではなく家族や担当ケアマネジャーであるケースがほとんどです。とくに、介護保険サービスの計画を立てるケアマネジャーにとっては、施設の情報が簡潔かつ的確に伝わるホームページの存在が、判断材料として大きな役割を果たします。
ホームページ上で
- 提供しているサービス内容
- 1 日の流れ
- 利用料金の明確さ
- 利用者の声
- スタッフ紹介
- 送迎範囲や対応エリア
などを明示しておくことは、「この施設なら任せられる」と感じてもらう第一歩となります。
また、ケアマネジャーが複数の候補施設を一括で提案することも多いため、他施設と並べて比較された際に「印象に残るサイトかどうか」「信頼感を与えるかどうか」が大きな差別化ポイントとなります。
施設の「見える化」としてのホームページ活用
今や、ホームページは単なる会社案内の延長ではなく、施設の信頼性や特色を伝える「営業マン」的な存在です。対面での営業が難しい福祉業界において、ホームページを通じて安心感や親しみを与えることが、見学・問い合わせにつながる大きな要因となります。
特に注力すべきなのが、「見える化」です。以下のような情報を写真や動画で可視化することで、利用者や家族が施設の雰囲気を事前に把握しやすくなります。
- 実際の利用風景(食事・レクリエーション・機能訓練)
- スタッフの笑顔や挨拶シーン
- 清潔感のある館内の写真
- 季節のイベント・取り組み紹介
- 利用者の声(許諾の上での掲載)
こうした「温度感」が伝わるコンテンツこそ、数字では測れない安心感や信頼感を訴求する最大の武器になります。
今後、同一エリア内でデイサービス施設がますます増えていく中で、「どの施設も似て見える」時代が来ます。そのときにこそ、ホームページでどれだけ自施設の強みや魅力を発信できているかが、選ばれるかどうかを大きく左右します。
まだホームページを持っていない施設や、5 年以上前に作ったまま更新されていない場合は、今こそ「見られる・選ばれる」ための情報発信を強化すべきタイミングです。
デイサービスのホームページに必要な 7 つの基本情報
デイサービスのホームページは、単なる施設案内ではなく、信頼と安心感を伝える重要な接点です。家族やケアマネジャーが比較検討する際、「わかりやすく」「網羅的に」「温かみをもって」情報が掲載されているかが、問い合わせや見学申込に直結します。
ここでは、デイサービスのホームページに必ず掲載しておきたい7 つの基本情報と、それぞれに求められるポイントを解説します。
1. 施設の概要(理念・沿革・運営方針)
まずは、**「どんな思いで運営されている施設なのか」**を明確に伝えることが大切です。介護施設は“人”の信頼で選ばれるため、経営理念や創業の背景、地域との関わり、今後のビジョンなどを丁寧に記載しましょう。
おすすめポイント:
- 「私たちの想い」などの見出しで温かみを演出
- 創業者や管理者のメッセージを掲載すると信頼度が増す
2. サービス内容の詳細
利用者にとって一番重要なのが、**「何ができるのか」**です。入浴、食事、機能訓練、レクリエーションなど、日常的なサポート内容を具体的に示すことで、安心材料となります。
記載例:
- 「個浴での入浴支援」「管理栄養士監修の食事」「理学療法士による個別訓練」など
- 各サービスごとに写真をつけると効果的
3. 対応可能な医療・介護体制
医療ニーズの高い方や要介護度の高い方が増える中、**「どこまで対応できるのか」**はとても重要な選定要素です。
記載すべき内容:
- 看護師の常駐有無
- 処置対応(インスリン、胃ろう、バルーンカテーテル等)
- 医療機関との連携体制
これらの情報を明示することで、医療的ケアが必要な方やそのご家族にも安心してもらえます。
4. 1 日の過ごし方(タイムスケジュール)
利用者がどんな 1 日を過ごすのか、生活のイメージを具体化する情報です。「〇時に到着、〇時に体操、〇時に食事」など、時間軸に沿って活動内容を掲載しましょう。
ポイント:
- イラストや表で視覚的に示すと理解されやすい
- 季節ごとのイベントも織り交ぜると印象アップ
5. ご利用料金・制度の説明
「費用がわかりにくい」ことは問い合わせを妨げる最大要因です。介護保険適用時の自己負担額や、食費・送迎費用などの実費分も、なるべく具体的に記載しましょう。
補足すると良い情報:
- 1 割・2 割負担の料金例
- 各種減免制度・助成制度への対応
- 見積もり依頼・相談の案内
6. アクセス情報と送迎対応エリア
地図と一緒に、「どの地域まで送迎可能か」を具体的に記載しましょう。送迎対応エリアは想像以上に施設選びの重要ポイントです。
おすすめ掲載内容:
- 対応地域の地図(○○ 市全域、△△ 町一部など)
- 送迎時間帯の目安
- 駐車場の有無・バリアフリー対応状況
7. スタッフ紹介と写真
介護サービスにおいて、「誰が対応してくれるか」はサービスの質を判断する最大要素です。スタッフの写真、保有資格、メッセージなどを掲載することで、親近感と信頼感が高まります。
掲載の工夫:
- スタッフの笑顔の写真を多用
- 「○○ さんに話を聞いてみたい」と思わせるプロフィール設計
- 男女比や年代構成も紹介すると雰囲気が伝わる
これら 7 つの要素を丁寧に構成すれば、初めてホームページを訪れた方に対しても、信頼感・安心感・魅力がしっかり伝わるページを作ることができます。
特にデイサービスのような介護施設では、「空きがあるか」よりも「安心して任せられるか」が選ばれる決め手です。内容が薄いホームページはその時点で候補から外れる可能性が高いため、上記の情報は確実に盛り込んでおきましょう。
信頼感を高めるホームページの構成とデザインのポイント
デイサービスのホームページにおいて、第一印象で信頼感を与えられるかどうかは極めて重要です。特に、閲覧者の多くが高齢者の家族やケアマネジャーであることを考えると、**「安心できる」「丁寧そう」**と感じてもらえるデザインと構成は必須です。
ここでは、信頼感を高めるために押さえておきたい5 つのポイントを紹介します。
トップページのファーストビュー設計
最初に目に入るファーストビューこそが、施設の印象を左右します。雑然とした印象や情報が詰まりすぎているレイアウトでは、**「古そう」「管理が行き届いていなそう」**といったマイナスイメージを持たれてしまいます。
理想的なファーストビューとは:
- やさしい色調とシンプルなデザイン
- キャッチコピーで「施設の想い」や「強み」を伝える
- 実際の施設写真(外観・笑顔の利用者・職員)を大きく掲載
特に「温かみ」や「清潔感」を印象付けるビジュアルは、信頼感の醸成に直結します。
写真と動画の使い方(施設・食事・レクリエーション)
文字だけでは伝わらない、施設の雰囲気やサービスの質を補完するのがビジュアル要素です。リアルな写真や短い紹介動画を使うことで、臨場感と安心感が伝わります。
効果的な活用方法:
- 入浴や食事、レクリエーション風景を明るく自然な形で撮影
- 写真のサイズや配置を統一し、雑多な印象を避ける
- 動画は 60〜90 秒程度で、雰囲気を伝える短尺に
プロカメラマンによる撮影が理想ですが、スマホでも光の使い方や構図を意識すれば十分魅力を伝えることができます。
ご利用者の声や家族の声の掲載方法
実際に通われている方やそのご家族の声は、**何よりも説得力のある“証拠”**になります。
掲載のコツ:
- 実名やイニシャル、年齢を添えると信憑性が高まる
- 「不安だったけど通って良かった」といった共感を呼ぶ内容を意識
- 写真とセットで掲載するとより印象的
ただし、過剰に“作られた感”が出ると逆効果になりかねないため、ナチュラルな言葉での紹介が望まれます。
実績・導入事例の見せ方
**「この施設なら大丈夫そう」**と思わせるには、数字や実績、表彰歴などの明示が効果的です。
例:
- 「月間 ○○ 名の利用者」「開設から ○ 年」
- 自治体との連携事業の実績
- 感染対策や介護品質に関する第三者評価
ただし、数字ばかりが並ぶと読み手が疲れてしまうため、アイコンやグラフを使って視覚的に整理しましょう。
スマホ対応(レスポンシブ)の重要性
今や Web 閲覧の7 割以上がスマートフォンからといわれており、シニア層の家族やケアマネジャーも例外ではありません。
スマホ対応が必須の理由:
- スマホで見づらいサイトは即離脱される
- 電話・地図・LINE 連携など、スマホでの行動導線が重要
- Google 検索順位にもスマホ対応かどうかが影響
レスポンシブ対応は当然として、「タップしやすいボタン配置」「読みやすい文字サイズ」「スクロールしやすい設計」など、スマホ利用者の行動を意識した UX 設計が求められます。
これらのポイントを意識して構成・デザインを設計することで、デイサービスのホームページは**「比較されても選ばれる存在」**になります。
とくに高齢者の家族にとっては、Web サイトから受ける印象が施設選びの決め手になるケースが多いため、見た目や体裁以上に**「どれだけ信頼される構成になっているか」**が重要です。
競合サイトの事例比較|選ばれているデイサービスの共通点
地域の検索で上位表示されているデイサービスのホームページには、いくつかの共通する特徴があります。単に情報が整っているだけでなく、「この施設にお願いしたい」と感じさせるための設計・内容・伝え方に工夫が凝らされています。
ここでは、実際に上位表示されているデイサービスの Web サイトを参考にしながら、競合に勝てるホームページ作りのヒントを紹介します。
実際に上位表示されているサイトの共通要素
検索順位が高いホームページは、SEO だけでなくユーザー体験を重視した設計になっています。共通点として、以下のような要素が挙げられます。
- 施設の特徴を冒頭で明示(例:「認知症対応」「リハビリ強化型」など)
- ページの表示速度が速く、スマホでも快適
- スタッフ紹介や活動報告ブログなど、更新頻度が高い
- 写真・動画が多く、施設内の雰囲気が伝わりやすい
- Google ビジネスプロフィールや SNS との連携がある
特に、**検索キーワード(例:地域名+デイサービス)**を意識した見出しや本文の構成が SEO に効果を発揮しています。
施設の「らしさ」を伝えるブランディング例
競合と差別化するには、その施設ならではの“らしさ”を打ち出すことが欠かせません。上位サイトの多くは、ブランドコンセプトを明確に打ち出しています。
例:
- 「笑顔があふれるアットホームな空間」
- 「理学療法士が常駐する専門的なリハビリサービス」
- 「ご家族とのつながりを大切にしたサポート体制」
このような施設の強みを、キャッチコピーや導入文に盛り込むことで、訪問者の心に響く印象を与えています。
また、ロゴや色合い、フォントなどのトーンを統一することで、ブランディングが一貫して伝わる設計になっている点も特徴です。
他と差がつく情報の出し方とは?
単に必要情報を並べるだけでは、他施設と大差のない「よくあるデイサービスサイト」になってしまいます。差別化できる情報の出し方には以下のような工夫があります。
- 利用者ごとの一日スケジュール例を紹介(写真付き)
- 食事の献立表や「栄養士コメント」を週ごとに掲載
- 送迎エリアをマップ付きで明示
- 職員の資格や研修歴など、ケアの質を裏付ける情報を追加
また、「この施設は安心できそう」と思わせるには、Q&A や利用者の声を自然な形で散りばめるのが有効です。
選ばれるデイサービスのホームページは、「施設を知るための情報源」だけでなく、“ここに任せたい”と思わせるツールとして機能しています。
SEO を意識しながらも、単なる検索上位ではなく、感情に訴えかける設計と構成を意識することが、競合との差を生み出すカギになります。
ホームページ制作の流れ|準備から公開・運用までの全体像
デイサービスのホームページ制作は、「ただ作ればいい」というものではありません。施設の魅力を正しく伝え、利用検討者に選ばれるサイトを作るには、計画的なステップと関係者との連携が欠かせません。
ここでは、実際の制作プロセスを 4 つのステップに分けて、全体の流れと注意点を解説します。
1. 情報整理と原稿作成(施設スタッフとの連携)
まずは、掲載する情報の洗い出しと整理からスタートします。
この段階で重要なのは、スタッフ全員が「何を伝えたいのか」「誰に向けたサイトなのか」を共通認識として持つことです。
準備する主な内容
- 施設の特徴や理念、運営方針
- 提供サービスとその詳細(例:入浴・リハビリ・レクリエーション)
- 料金体系と制度の説明
- スタッフの紹介や写真
- 一日のスケジュールや利用の流れ
ホームページ制作会社によっては、ヒアリングをもとに原稿作成を代行してくれる場合もあります。
ただし、施設の専門性やニュアンスは現場のスタッフにしかわからない部分も多いため、必ず原稿の確認・監修は自施設で行うようにしましょう。
2. 写真撮影・デザイン制作
原稿がある程度まとまった段階で、写真撮影やデザイン作業に移ります。
ここでは、実際の施設の雰囲気を伝える「視覚的な要素」が非常に重要です。
撮影で用意しておきたいもの
- 外観・内観の清潔感が伝わる写真
- 食事・レクリエーション中の様子(利用者が映る場合は同意取得必須)
- スタッフの笑顔や対応風景
デザインの方向性は「やさしく」「安心感のある」テイストが好まれる傾向にあります。
制作会社と事前に方向性をすり合わせ、施設カラーやイメージに合った仕上がりに調整しましょう。
3. 制作会社とのやりとりと進行管理
ホームページ制作は、施設と制作会社の“二人三脚”で進めるプロジェクトです。
やりとりの頻度や対応スピードによって、完成までの期間や品質が大きく左右されます。
スムーズに進行させるためのポイント
- 担当者を一人決めて、窓口を一本化する
- 修正依頼やチェックはまとめて伝える
- 不明点があれば遠慮せず確認する
また、スケジュールの遅延を防ぐために、最初に全体の進行スケジュールを共有しておくことが重要です。
特に、「介護報酬改定に間に合わせたい」「◯ 月から広告出稿したい」などの公開目標がある場合は早めの準備を心がけましょう。
4. 公開後の運用体制とサポート
ホームページは「公開して終わり」ではありません。
むしろ、公開後の運用・更新こそが重要なフェーズです。
運用で必要になる作業
- 最新情報の更新(空き状況、イベント告知など)
- ブログ・お知らせの投稿
- 利用者の声や写真の差し替え
- 法改正に伴う記載内容の修正
保守・更新サービスがついている制作会社であれば、専門的な作業も任せられるため安心です。
ただし、更新頻度が高くなるような施設の場合は、CMS(ブログ投稿システム)を導入するかどうかも検討ポイントです。
このように、ホームページ制作は「設計・制作・運用」まで一貫した流れで取り組む必要があります。
施設の魅力を最大限に伝えるためにも、社内での連携と制作会社との密なコミュニケーションを大切に進めましょう。
デイサービスのホームページ制作にかかる費用相場
ホームページ制作を検討する際、最も気になるのが「どれくらいの費用がかかるのか?」という点ではないでしょうか。
特に、デイサービスのような福祉施設では、限られた予算内で最大限の効果を出すことが求められます。
ここでは、初期制作費用・月額費用・オプション費用の相場感をわかりやすく解説します。
初期費用の目安(テンプレート型/オリジナル型)
ホームページの制作費用は、主に「テンプレート型」と「オリジナル型」で大きく異なります。
-
テンプレート型(20 万円〜40 万円程度)
既存のデザインテンプレートを使い、文章や写真を差し替えて制作するスタイル。
費用を抑えつつスピーディに公開できるのがメリットです。
ただし、他施設とデザインが似通いやすいため、差別化しにくい面もあります。 -
オリジナル型(50 万円〜100 万円程度)
施設の特徴やブランドに合わせて一からデザイン・構成を設計する方法です。
デザイン性や使いやすさを重視し、「選ばれる施設」になるための戦略的な構成が可能になります。
写真やコピーにもこだわりたい場合はこちらがおすすめです。
月額運用費・更新費の相場
ホームページを公開した後も、維持・更新には一定の費用がかかります。
- サーバー・ドメイン管理費:年間 1 万円〜2 万円程度
- 月額運用費(保守・軽微な更新対応含む):月額 5,000 円〜15,000 円程度
- 更新作業代行(都度依頼制):1 回あたり 5,000 円〜20,000 円程度(内容による)
多くの制作会社では、保守契約や月額プランを提供しており、セキュリティ対策やバックアップ、軽微な修正なども依頼できます。
内部スタッフで更新できる CMS(投稿システム)を導入する場合は、導入時に追加費用が発生する場合もあります。
文章作成・写真撮影の費用感
ホームページの品質は、「中身(コンテンツ)」次第とも言えます。
文章や写真のクオリティが高いほど、利用者や家族の安心感・信頼感につながります。
- 文章作成(プロによる取材・ライティング):1 ページあたり 2 万円〜4 万円
- 写真撮影(カメラマン出張・半日):3 万円〜8 万円
※撮影内容や地域によって変動します
プロによる撮影・取材を組み合わせることで、施設の「空気感」や「らしさ」を伝えることが可能です。
利用者の笑顔やスタッフの対応風景など、写真の持つ説得力は非常に大きな要素です。
チラシ・パンフレット連動の制作事例
最近では、ホームページと一緒に紙媒体(パンフレット・チラシ)を連動して制作するケースも増えています。
- パンフレット制作(A4/三つ折り):5 万円〜15 万円程度
- チラシ(配布用/イベント用):1 万円〜5 万円程度
- 連動パック割引がある制作会社も多く、同じデザインテイストで統一することでブランディング効果が高まります。
特に地域密着型のデイサービスでは、チラシ・パンフレットで問い合わせを得てからホームページを見てもらうという流れも多いため、連携したデザイン戦略が有効です。
まとめ
ホームページ制作費用は「見た目」だけでなく、「伝える力」や「安心感」をどこまで表現できるかによって価値が変わってきます。
デイサービスにおいては、単なる情報発信ではなく、利用検討者とその家族に“信頼”を届けるツールとして考えることが大切です。
予算に応じた最適なプランを見つけ、後悔のないホームページ制作を進めていきましょう。
サブスク型(定額制)ホームページ制作の選択肢とメリット
近年注目されているのが、サブスク型(定額制)ホームページ制作という選択肢です。
従来の一括払い型と比べ、初期コストを抑えながら運用・更新を継続しやすいという特徴があり、特に中小規模のデイサービス事業者にとっては魅力的な選択肢になっています。
このセクションでは、一括払いとの違いやメリット、契約時の注意点について詳しく解説します。
一括払いとの違いとは?
従来型のホームページ制作では、以下のような構成が一般的でした:
- 初期費用:50 万〜100 万円程度(設計・デザイン・構築費用)
- 運用費用:月額数千円〜(サーバー代や保守管理費)
このような「一括払い型」は、まとまった初期投資が必要なため、導入のハードルが高いと感じる施設も多いのが現状です。
一方で、サブスク型(定額制)の場合:
- 初期費用:0 円〜5 万円程度に抑えられることが多い
- 月額費用:5,000 円〜15,000 円程度で、制作+保守+更新サポート込み
つまり、導入しやすく・継続しやすい料金体系で、必要な機能を無理なく利用できるのが特徴です。
サポート付きで更新しやすい仕組みとは?
サブスク型ホームページでは、単なる制作だけでなく「運用支援」もセットになっているケースが多数あります。
- 文章の修正・写真の差し替え依頼が月に ◯ 回まで無料
- お知らせ投稿など、代行での更新対応
- 定期的なアクセス解析レポートの送付
- CMS(更新システム)を使った自分での簡単な更新も可能
これにより、施設内に専門の IT 担当者がいなくても、常に最新情報を掲載しやすい体制が整います。
また、スマートフォンでの表示対応(レスポンシブデザイン)やセキュリティ更新など、技術的な保守管理も自動的に対応されるため、安心して任せられる仕組みが魅力です。
契約前に確認すべき注意点
サブスク型はメリットが多い一方で、事前にしっかり確認しておきたいポイントも存在します。
-
最低契約期間の有無(例:12 ヶ月〜24 ヶ月の縛り)
途中解約すると違約金が発生するケースもあるため、契約書を必ず確認しましょう。 -
解約後のデータ引き渡し可否
契約終了後にホームページのデータがもらえない(使い回せない)プランもあります。
将来的な乗り換えを想定した柔軟な設計かをチェックすることが重要です。 -
更新範囲・回数の制限
「月に 1 回まで無料」など制限がある場合、頻繁な更新が必要な施設には不向きな場合があります。 -
カスタマイズの自由度
テンプレート中心の構成が多く、オリジナリティが出しにくい場合もあるため、事前にデモサイトを確認しておくと安心です。
まとめ
サブスク型ホームページ制作は、導入コストの低さ・更新のしやすさ・運用サポートという点で非常に有効な選択肢です。
特に、人手や時間の限られた中小規模のデイサービス施設にとっては、情報発信を継続するうえで大きな助けになります。
ただし、「ずっと月額を払い続けることになる」「自由度が限られる場合がある」といった側面もあるため、契約前には自施設の運用方針に合った仕組みかどうかをしっかり比較・検討することが大切です。
集客・信頼に効くオプション機能の活用例
デイサービスのホームページは、単に情報を掲載するだけでなく、「集客」や「信頼獲得」につなげるための戦略的なツールとして活用することが重要です。
そのためには、標準機能に加えていくつかの「オプション機能」を組み込むことで、より多くの利用者やご家族、求職者との接点を増やすことが可能になります。
ここでは、特に効果的なオプション機能の活用例を紹介します。
LINE 連携・お問い合わせフォームの設置
高齢者本人ではなく、ご家族が情報収集の主導権を握っているケースが多いデイサービス業界では、気軽に問い合わせができるチャネルの整備がカギになります。
- LINE 公式アカウントとの連携:施設の情報配信やイベント案内をタイムリーに通知でき、チャットで気軽に質問も可能。
- お問い合わせフォーム:24 時間受付可能なフォームを設置することで、電話対応が難しい時間帯でも機会損失を防げます。
LINE やフォームを通じた相談が、施設見学や契約のきっかけになることも多く、導線設計の工夫が来所率を大きく左右します。
Google マップ・口コミとの連携
検索結果に表示される**Google ビジネスプロフィール(旧:Google マイビジネス)**の整備も、今やホームページと同等に重要な施策です。
- Google マップとの連携:施設の場所を明確に伝えるだけでなく、口コミ・星評価を通じて第三者の信頼感を演出できます。
- 口コミ誘導ボタンの設置:ホームページ内からスムーズに口コミ投稿に誘導することで、信頼感を積み重ねることができます。
また、施設名+地域名で検索した際にマップ上位に表示されるかどうかは、ローカル SEOの観点でも重要です。
採用情報ページとスタッフ募集導線
デイサービス運営において、人材確保は最重要課題のひとつです。ホームページに採用情報ページを設けておくことで、求人媒体に依存せずに応募者を獲得できる可能性が広がります。
- 「スタッフの声」や「1 日の仕事の流れ」などの掲載は、職場の雰囲気を伝えやすくなり、求職者の不安を払拭。
- 応募フォームの導入や、Indeed・ハローワークなど外部求人サイトとの連携で導線を拡張。
特に、施設の理念や働く魅力を丁寧に発信することで「共感採用」につながるケースも多く、長期的な定着率にも寄与します。
アクセス解析・改善 PDCA の導入
ホームページは「作って終わり」ではなく、公開後に改善を重ねて成果を最大化させるフェーズが重要です。
- Google アナリティクスによるアクセス解析:どのページが見られているか、どこで離脱されているかを把握できます。
- ヒートマップ分析の導入:ユーザーが実際にどこをクリック・注視しているかを可視化。
- 月次レポートによる改善提案:制作会社や担当者と PDCA を回すことで、より伝わる・成果の出るサイトへと進化させていきます。
このようなデータをもとに、「ユーザー視点での改善」を継続できる仕組みを整えておくことが、ホームページの資産価値を高めるカギとなります。
まとめ
集客や信頼性の向上を目指すなら、**オプション機能の導入は単なる“追加”ではなく“投資”**と捉えるべきです。
LINE 連携やフォーム設置は今すぐにでも始められる施策ですし、口コミ強化や採用導線の整備は中長期的に大きな効果を生み出します。
アクセス解析による改善体制まで整えられれば、デイサービスのホームページは「営業・採用・信頼構築を担う多機能ツール」へと進化していきます。
よくある質問(FAQ)
デイサービスのホームページ制作を検討している施設様から、よくいただく質問をまとめました。これから制作を始めるにあたり、不安や疑問を解消しておくことはとても大切です。以下の Q&A は、実際に多くの施設が悩まれるポイントをカバーしています。
Q. ホームページに写真やロゴがなくても大丈夫?
写真やロゴがない状態でも制作は可能です。
ただし、施設の雰囲気や特色を伝える上で、写真はとても重要な役割を果たします。外観や内装、レクリエーションの様子、食事の風景などを掲載することで、利用検討者やそのご家族に安心感を与えることができます。
ロゴがない場合も、仮のロゴを制作したり、文字ベースでシンプルに構成することもできます。必要に応じてロゴ制作のオプションもご提案可能です。
Q. 文章は自分たちで用意するべき?
原稿はご自身で用意していただくことも可能ですが、専門ライターによる代行もおすすめです。
施設スタッフの皆さまが書かれた文章には「現場のリアル」がにじみ出てとても良いのですが、読みやすさや SEO 対策を意識したライティングには一定のスキルが求められます。
文章構成のたたき台をこちらでご用意し、ヒアリングしながら共同で仕上げていくスタイルも人気です。「忙しくて文章を考える時間がない」という場合は、ぜひプロにお任せください。
Q. ホームページ公開後のサポート内容は?
制作会社や契約プランによって異なりますが、基本的には以下のようなサポートが一般的です。
- 軽微なテキスト修正や写真差し替え
- お問い合わせフォームや地図などの機能保守
- セキュリティやドメインの管理代行
- トラブル時の緊急対応
サブスク型のホームページ制作サービスでは、毎月の更新サポートやアクセスレポートの提供がセットになっている場合もあります。どこまで対応可能かは事前に確認しておきましょう。
Q. 更新作業はどうすればいい?
更新のやり方は「自分で行う」か「制作会社に依頼する」の 2 通りがあります。
- ご自身で更新される場合は、WordPress などの CMS を使った構成であれば、ログインして直感的に編集できます。
- 制作会社に依頼する場合は、月額料金に更新作業が含まれているか確認しましょう。
特にデイサービスのような介護施設では、「日常の活動レポート」「空き状況の更新」など小まめな情報発信が信頼につながるため、更新体制はあらかじめ計画しておくと安心です。
まとめ
ホームページ制作は専門的な工程も多いため、最初は不安がつきものですが、信頼できる制作パートナーと連携することでスムーズに進行可能です。
不明点があれば遠慮なく相談し、納得した上で制作をスタートしましょう。FAQ に挙げたような疑問は、実際の打ち合わせでも丁寧に確認しながら進めていきますので、安心してご依頼いただけます。
制作会社の選び方と依頼時のチェックポイント
デイサービスのホームページ制作を成功させるためには、信頼できる制作会社を選ぶことが非常に重要です。介護業界ならではのニーズを理解し、施設の魅力を的確に表現してくれるパートナーを見つけることで、集客や信頼感の向上につながります。ここでは、制作会社選びの際に確認すべきポイントを詳しく解説します。
地域密着型 vs 全国対応の違い
制作会社には、地域密着型と全国対応型があります。それぞれに特徴があるため、自施設のニーズに合った方を選びましょう。
- 地域密着型のメリット:訪問対応や現地撮影がしやすく、細かなニュアンスのすり合わせが得意。地域の介護事情に精通しているケースも多い。
- 全国対応型のメリット:価格が比較的安価な傾向があり、テンプレート型やオンライン完結型など、選択肢が豊富。スピード感を重視する施設に向いています。
どちらを選ぶにしても、実際のコミュニケーション体制や対応の丁寧さを確認することが大切です。
実績・介護業界への理解があるか?
介護業界には、高齢者や家族に安心感を与える情報設計や、介護保険制度など専門的な知識が求められます。そのため、以下のような実績・理解度を確認しましょう。
- 過去に介護施設や福祉事業のホームページを制作した実績があるか
- レクリエーション、送迎対応、医療連携などの内容に詳しいか
- ご家族やケアマネージャーへの情報提供を意識した構成に慣れているか
こうした点が不足していると、「きれいだけど伝わらないホームページ」になってしまう恐れがあります。
契約内容・解約条件のチェックポイント
ホームページ制作は一度作ったら終わりではありません。契約内容をしっかり確認することで、トラブルや無駄な出費を防ぐことができます。
特に注意したいのは以下の点です。
- 契約期間と自動更新の有無
- 月額費用に含まれる更新サポートの範囲
- 解約時の費用・ドメインやデータの取り扱い
- デザインや写真の著作権の所在
長期的な運用視点で、安心して付き合えるかどうかが重要です。
実際の担当者とコミュニケーションの重要性
制作の進行中は、**担当者とのやりとりが頻繁に発生します。**そのため、次のようなポイントにも注目しましょう。
- レスポンスが早く、丁寧に説明してくれるか
- 専門用語をわかりやすく説明してくれるか
- 初回打ち合わせで施設の想いやこだわりをしっかり聞いてくれるか
とくにデイサービスでは、「利用者やご家族にどんな印象を与えたいか?」といった施設ごとの温度感を理解してもらえるかどうかが重要です。制作会社との相性が、サイトの仕上がりを大きく左右します。
まとめ
制作会社選びは「どこに頼むか」だけでなく、「誰と進めるか」も含めた総合的な判断が求められます。実績・対応力・信頼性を丁寧にチェックし、自施設の想いを形にしてくれるパートナーを見つけましょう。しっかり比較・検討して、納得のいくホームページ制作につなげてください。
まとめ|信頼されるデイサービスを目指すなら、ホームページから整えよう
デイサービスの運営において、利用者やそのご家族、地域住民からの信頼を獲得することは何よりも重要です。パンフレットやチラシだけでは伝えきれない施設の雰囲気や魅力、スタッフの温かさ、サービスの質などをしっかりと発信するには、ホームページの整備が欠かせません。
特に高齢者福祉の分野では、選ぶ側が慎重に情報収集を行い、「ここなら安心して任せられる」と思える要素が求められます。そのためには、見た目の美しさだけでなく、情報の整理・伝え方・構成の工夫が必要です。ファーストビューの印象や、ご利用者の声、スタッフ紹介、写真・動画の活用など、信頼を後押しする工夫をサイト全体に散りばめましょう。
また、スマートフォン対応や更新性の高さ、LINE や地図連携といった機能面も、現代のユーザーにとっては当たり前の基準です。定額制(サブスク)やサポート体制の整った制作プランを選ぶことで、公開後も安心して運用を続けられます。
介護の現場では日々多忙な業務に追われることも多いため、ホームページ制作にあたっては、信頼できる制作会社との連携が不可欠です。介護業界への理解があり、丁寧にヒアリングを行ってくれるパートナーを見つければ、施設の想いがしっかりと伝わるサイトが実現できます。
これからの時代、施設の魅力や理念を「伝える力」が選ばれる理由になります。信頼されるデイサービスを目指すなら、まずはホームページから見直してみることが大切です。
ホームページ制作のご相談はお気軽にどうぞ
(株)KUBOYA では、経済産業省認定の中小企業診断士(経営コンサルタント唯一の国家資格)兼ソフトウェアエンジニアである代表が、ホームページ制作に関するあらゆるご相談に親身に対応しています。
「どんな内容を載せればよいかわからない」「コストを抑えて信頼感のあるホームページを作りたい」「定額制で気軽に始めたい」など、貴社の状況に合わせて、最適なご提案をいたします。
(株)KUBOYA 代表:久保谷太志 経歴
大手精密機械メーカーにて画像処理システムの販売及び構築業務に携わった後、事業会社にて社内システム開発・Web マーケティングを経験。2025 年に(株)KUBOYA を設立し、ホームページ制作・自社開発 SaaS・モバイルアプリ開発などを幅広く手がけています。
中小企業ならではの課題やご要望に柔軟に対応し、制作後の運用まで見据えたサポートを大切にしています。
ホームページ制作に関する無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
📘 続けて読みたい関連記事
👉 介護施設ホームページ制作で失敗しない方法|信頼を得る構成とデザインのコツとは?
📘 続けて読みたい関連記事
👉 ホームページ制作の流れを徹底解説|打ち合わせから公開・運用までの全ステップ











